本の虫だった少女が夢見たのは、国連職員になること
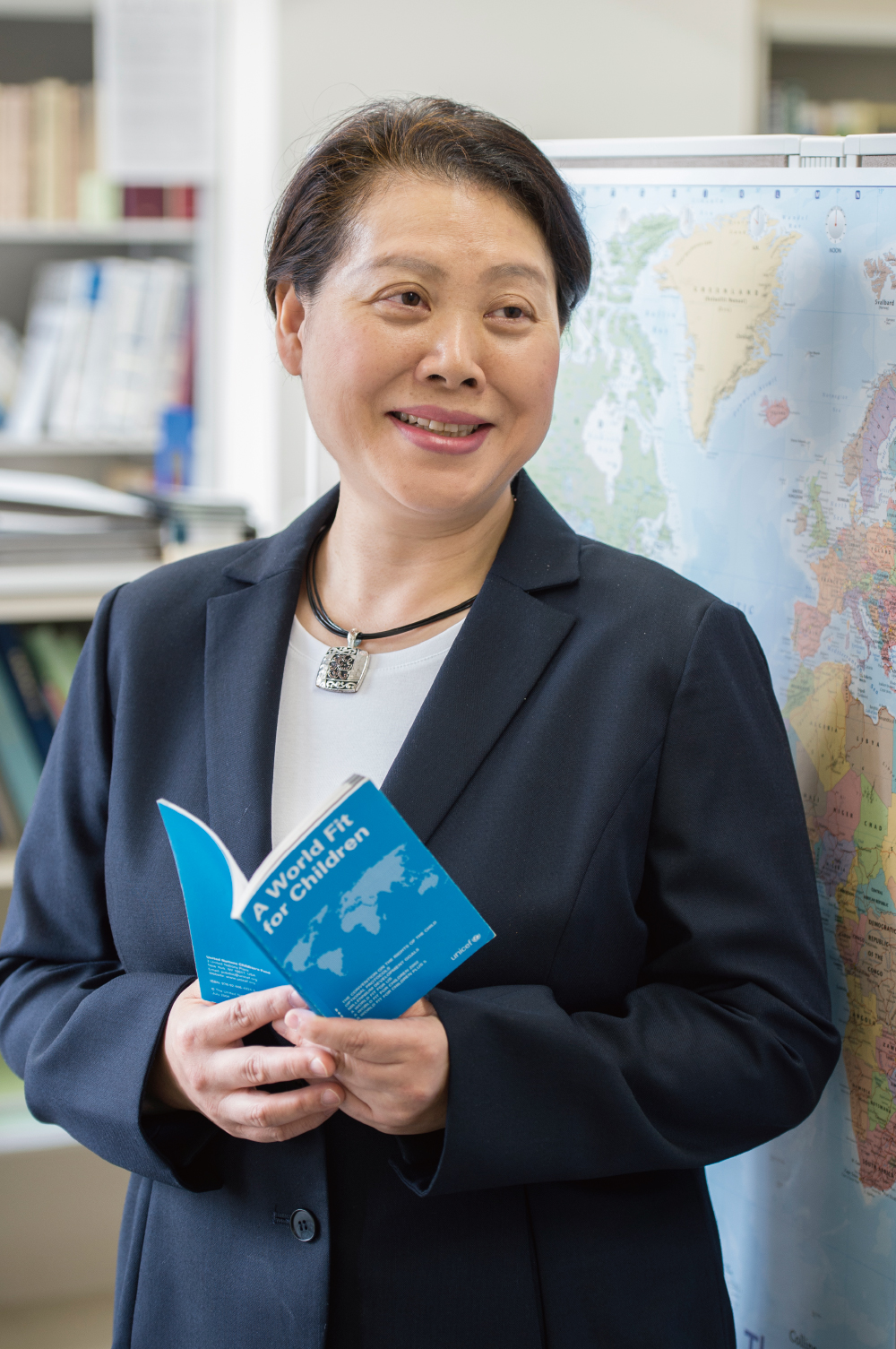
「人や社会のために役立つような仕事をしたい」。それは、子どもの頃からずっと変わらない思い
2017年3月、大谷美紀子は国連の「子どもの権利委員会」委員に就任し、新たな舞台に立った。日本人としては初の就任で、そのぶん国内外から寄せられる期待も大きい。大谷は国際家事事件を専門とする弁護士で、国際人権問題、なかでも女性や子ども、外国人といった弱い立場に立たされることが多い者の権利を守るために力を尽くしてきた。加えて、日弁連やNGOでの活動を通じ、人権教育の分野でも積極的な活動を続けている。子どもの頃から一貫して胸にあるのは、「人のため、社会のために役立つ仕事がしたい」という思いだ。意外なことに「本来は引っ込み思案」だとしながらも、大谷はその強い信念によって突き動かされてきた。そして、どのような立場、環境にあっても自らの存り方を常に問い、弛まぬ努力を重ねてきた。だからこそ、望んだ今日がある。
幼い頃から読み物、活字が大好きで、気がついたら本の虫。文学全集の類はもちろんのこと、読む本がなくなると百科事典を片っ端から読んでいました。もともと引っ込み思案なのに加えて、小学校時代は父の転勤などで何度か転校したこともあって、本ばかり読んでいましたね。たくさんの本を読むなかで、社会問題に対する関心も強かったし、大人びたところがあったのでしょう。同世代の子どもとは、ちょっと違う世界にいたように思います。
通っていた滋賀県の膳所高校は、圧倒的に男子が多い進学校で、個性的な先生や、問題意識の高い生徒もいて刺激的でした。ただこの頃、私は若干ぐれていて、スカートの丈を長くし、パーマかけてと、不良ぶっていたんです。
実は中3の時、先生からセクハラを受け、それを学校に直訴したものの、結局納得のいく対応をしてもらえなかったという一件があったんですね。そしてもう一つ。高校に進学してすぐの頃、肺炎を患ってしばらく学校を休んだのですが、担任は五月病だと決めつけてしまった。ちゃんと診断書を提出しているのに、「学校で何かイヤなことでも?」という対応をされた。連続的に起こった出来事から、私は一時期、学校不信に陥っていたわけです。だから“見た目”不良ぶり、学校が禁止するアルバイトをしたりしていたのです。
でも、勉強だけはすごく真面目。受験を意識していたわけではなく、自分に挑戦する感じでしょうか。次はオール100点を取るぞ、10段階評価の成績で全部「10」を取るぞ、みたいな(笑)。「社会に出たら人の役に立てるような仕事をしたい」。漠然とながらも、そういう熱い思いだけはあって、実現するためには勉強しておかないと――そう考えていたのです。
その思いからすれば、世界のあらゆる社会問題の解決に取り組む「国連職員を夢見た」のも、うなずける話である。その進路を取るために、大谷は難関な受験を突破して上智大学に進学。同大学の法学部に国際関係法学科が新設されて間もない頃で、大谷は3期生として、同じく国連職員や外交官などを志す学生たちと共に学び始めた。
法学部ですから、当然必修の法律科目があるんですけど、あまり興味がなくて、国際経済や国際政治、国際機構論といった科目を熱心に勉強していました。ですが、早くも1年の夏あたりから悶々とし始めたのです。
きっかけは、アメリカが1984年にユネスコを脱退したこと。国連機関に対して、「過度に政治化している」という見方があることを初めて知り、一方で、アメリカの一国主義的な動きも知った。私の夢は世界平和ただ一つで、それがストレートに国連とつながっていたから、少なからずショックでした。ほかにも自分の青臭さに気づく場面があって、次第に「国連で本当にやりたいことができるんだろうか」という疑問が浮かんできたのです。そもそも「国連の中のどこで」が見えていなかったし、当時は、職員になるためのプロセスもクリアではなかった。悶々とする日々が続きました。
そんな頃、高校時代の友人から連絡が入ったのです。父親が他人の借金の保証人として債務を抱え、一家で長年住んだ土地を離れることにしたという。驚くとともに、何とかならないものかと思った私は、破産について調べてみたり、弁護士に相談するよう勧めたり、うるさくお節介をやいたんですね。でも、当の本人はあきらめちゃって、「もういい」と。これがショックでした。人の役に立ちたいという思いを支えに生きてきたのに、結局は私の独りよがり。本当に人の役に立つためには何が必要なのだろうかと悩みました。
結果、もう何になるか悩むのはやめよう、まずは自分の足場を決めて、そのなかでできることを精一杯やろうと決めたのです。友人の一件で、この時、法律に目が向きました。半ば直感でしたが、法律を専門分野にすれば、人や社会に役立つことに何かしら関係してくる、きっと無駄にはならないと思ったのです。司法試験を目指すと決めたのは、2年生の秋でした。
23歳で司法試験に合格。家事事件を通じて、人権教育に関心を抱く
周囲に法曹を目指す人がいなかったから、大谷は自力で情報収集して準備を整え、3年の春から勉強をスタートさせた。当時の司法試験は500人合格時代。「合格に10年かかる人もいる」と聞くなか、大谷は目標を立て、3年間で必ず合格すると決めた。早く社会に出て仕事がしたい、という気持ちが強かったからだ。そして実際に、大学を卒業した87年に合格。在籍していた国際関係法学科で弁護士になったのは、大谷が第1号である。
最初は司法試験のことも、勉強の仕方もわからなかったので、まずは調べるところからです。予備校に行く必要があると思ったので、授業料を確保するためにアルバイトもして。時間もお金ももったいないから、大学にある司法試験科目の授業はすべて取り、受験用の勉強の仕方と、“憲民刑”だけはLECで学ぶというスタイルです。「法律を足場に頑張る」と決めた以上、何としてでも合格する、やり抜くという意志は強かったと思います。
横浜修習中、検察官になるよう勧められたんですよ。私が国連に関心があることを知った修習担当の検事が、「留学をして“アジ研”の教官になるという道があるよ」と。国連を完全に忘れていたわけではないので、正直、グラッときたんですけど、最後は、やりたいことが自由にできる弁護士のほうがいいと選択しました。それと、当事者に近いところにいたかったから。今でも根っこは内気で、社交的ではないのですが、そのくせ、人と知り合ったり話したりするのが好き。矛盾しているけれど、困ったことにどっちも本当(笑)。しんどくても、結局のところ“人との仕事”が好きなんですよ。

大谷は、新麹町法律事務所で弁護士としてのスタートを切った。イソ弁の身で、まずはイロハを学び、弁護士として実力をつけようと、懸命にあらゆる事件に取り組んだ。同事務所においては2人目の女性弁護士ということもあり、なかでも多く扱ったのが家事事件である。次第に大谷は、ここに面白さとやりがいを見いだしていく。
弁護士といっても、当時はあまり専門化されていなかったので、様々な仕事を経験させてもらいました。ただ、いつの間にか「家事事件は大谷」という感じになったのは、女性のイソ弁が私だけだったからでしょう。それって裏返せば、差別的だと思ったりもしたのですが、やってみると、私が望んでいた“当事者との近さ”が実感できて性に合っていたのです。
それと、当時感じていたのが「弁護士って威張っているなぁ」ということ。例えば、女性の依頼者が家事事件で相談に来ると、対応する弁護士の物言いがきついと感じた。弁護士に相談するなど、もとより敷居が高く、相談者は緊張しているから話もあちこち飛んだりしますよね。「要点は何なの?」と言いたくなる気持ちはわかりますけど、私は、依頼者の話をていねいに聞くことにやりがいを感じていました。今も、その思いに変わりはありません。
人権問題に関心を持ち始めたのは、入所して3年ほど経った頃でしょうか。離婚や相続などの事件を通じて、社会のなかに差別が根深く残っていることに気づくうち、弁護士は人権を救済すると期待されているけれど、自分は人権について真剣に学んだことがあっただろうかと思い始めたのです。
弁護士の仕事は事後救済の面が強いでしょう。裁判での救済の重要性もわかっているのですが、裁判を起こすには費用も時間もかかって大変だし、法曹が被害者をさらに傷つけてしまう可能性もある。本当に痛みを感じている人を救えているのだろうか……。憲法の人権保障が現実となり、そもそも人権侵害が起きない世の中になることへの思いが強くなり、私の関心は、今でいうプリベンション(予防)に向いていったのです。
人権教育の勉強を始めるようになって出会ったのが、93年に国連が主催した世界人権会議で採択された宣言及び行動計画です。人権教育の重要性が述べられ、翌年には国連総会で「人権教育のための国連10年」の決議が採択されました。これこそが、私のやりたいこと――感銘を受けたと同時に、封印していたつもりの国連が戻ってきちゃった。高校生の頃は、「国連は平和のために頑張っている」程度の認識でしたが、この時にようやく、自分のやりたいことが明確に見えたのです。
米国留学を経て、独立。国際家族法の分野における〝第一人者〟に
人権教育の勉強を主眼に、大谷はコロンビア大学大学院に留学。これもまた大変な難関を突破してのことだが、「どうしても行きたかった先」での2年間は、大谷に十二分の実りをもたらした。夫や子どもと共に「ある国で暮らす外国人の立場」を経験したことも、のちに生きる財産となった。
世界人権会議を知った93年というのは、次女を出産したタイミングで、留学に飛びつける状態ではなかったんです。でも、どのみち2人の乳幼児を育てながら仕事を続けるのはかなりきついわけで、ならばいっそ娘たちを連れて留学し、育児が大変な時期は勉強期間に充ててしまおうと。とはいえ準備は大変だったし、夫が「僕も行く」と言い出したものだから、彼の準備も待って97年にやっと留学したんです。
国際人権法を学んだ大学院での2年間は、期待以上に有意義でしたね。法的なアプローチだけじゃなく、外交や経済、教育など、多面的な視点から人権を勉強したいという私の希望は、十分に叶えられました。そして並行して、国連人権高等弁務官事務所ニューヨーク事務所でインターンとして活動したことも貴重な経験。各国代表がどのように交渉するのか、専門家はどう動くのか、国連という多国間外交の生々しさを“内側”から見ることができたのは大きかったと思います。ほかにも、ティーチングアシスタントをする、論文を書いて発表する、といった私の目標をクリアできたのは、夫の支援があったから。最初は日本で留守番していてもらうつもりでしたが(笑)、結果的には大助かりだったというわけです。
もう一つ。メンターに出会ったことも、留学で得た大きな財産です。バングラデシュの元国連大使で、国連の事務次長も務めた男性なのですが、男女の平等に関して、これほど本質的な人はいないと思うほど立派な人。日本人女性が子連れで人権を勉強しに留学した心意気を評価してくださり、私が志を持ちながらも、臆病だったり、人からの批判に弱かったりという課題と闘っていることを本当に理解し、応援してくださった。今も家族ぐるみでお付き合いが続いています。感謝してもし切れません。

99年に帰国し、夫と共に大谷法律事務所(当時)を設立。もとより好きだった家族法、そして培った英語力を生かすべく、大谷は自分の専門を国際家族法事件に絞る。「アメリカの弁護士は専門化されている」ことに影響を受けたのと、自身が経験した“外国人の立場”というものへの理解をもとに、日本で暮らす外国人の家族問題に専門家として貢献したいと考えたからだ。
留学する前にも、国際離婚や外国人の交通事故事件を扱ったことはあるんです。事件自体は特別なものではなくても、外国人にとっては言葉の壁があり、日本の法システムもわからないから、大変なフラストレーションになる。「こんなに不安に感じるのか」という実感はありましたし、帰国当時、この分野での専門家はほとんどいなかったので、潜在しているニーズに応えようと考えたのです。何より、私は家族法が好きですし。経験と共に、自分の向き不向き、好き嫌いってわかってくるでしょう。ここが得意という分野をやったほうが情熱を持って臨めるし、スキルを磨くこともできるから、当然、依頼者に対する良いサービスにもつながる。今では「国際家族法なら大谷」と言っていただけるようになったのは、専門性を追求してきた一つの結果だと思っています。
並行して、日弁連の国際人権問題委員会や、NGO・市民社会で活動するなど、人権活動にも積極的にかかわってきました。外国人の司法アクセス問題にも長く取り組んでいて、東京弁護士会の公設事務所である東京パブリック法律事務所のなかに、外国人からの相談や依頼を専門的に受ける部門の設立にも動いてきました。その初代共同支所長として、約2年半仕事をした時期もあります。
業務と研究は、私の両輪なのです。ずっと勉強している国際人権は、知識としてはもちろん、事件へのアプローチや処理の仕方にも生きてくる。学問的な研究だけだと、現場を知らない机上の空論になってしまう危険があります。現場で事件を扱う私のバックボーンは、人の痛み、何が本質的な問題なのか難しさなのか、といったこと。これはすごく大事ですし、だからこそ、私のなかでは業務・活動と研究がうまく融合しているんですよ。
国際舞台の入口に立つ。思いを新たにし、全力で活動する日々
18歳未満の子どもの人権を保障する「子どもの権利条約」。この条約を結ぶ196の国・地域の履行状況を審査する委員会の委員選挙において、大谷はトップ当選を果たした。冒頭で触れたように、日本人としては初の委員就任である。「私個人というより、日本に対する信頼と期待の結果」だと本人は謙遜するが、これまでの実績と、貫いてきた信念が引き寄せた大舞台だ。
立候補者は国が指名する制度なので、外務省から声がかかった時は「願ってもない」という気持ちでした。ずっと「国際社会で役に立ちたい」と思い続けてきて、それが本当に叶うチャンスが巡ってきたのですから、まさに千載一遇といった感じ。だから、絶対に当選したかった。ただ、この選挙の投票権は、国にあるんですね。その国々によって事情も違うので、選挙活動とはいっても自分の力が届かない部分もあり、正直、大変ではありました。
投票権を持つ国と会うというのが選挙活動になるわけですが、私は「やれることは全部やる」と決めて、選挙の1年前から、毎月のようにニューヨークに渡り、各国の外交官と面談を重ねてきました。同時に、外務省も世界中で支援活動を行い、国と候補者が力を合わせて選挙に臨む。私のために、多くの外務省職員が動いてくれているのです。「落ちるわけにはいかない」というプレッシャーは強かったですね。
そんな選挙中に感じたことは、日本が積み重ねてきた国際貢献に対する世界からの信頼です。国の“内側”だけを見ていると、いろいろ言いたくなるけれど、外からの日本に対する信頼や期待値はとても高い。だから、私個人ではなく、日本全体が評価されての選挙結果だったと思うのです。そういうものを背負っての委員就任ですから、責任の重さを自覚しています。世界で18人の一人にしていただいたわけです。この条約の下、本当の意味で世界中の子どもの人権が守られることを実現するために、最大限力を尽くしたいと強く思っています。もう、何が苦手などと言っていられません(笑)。

今後は、国連の仕事が主軸になる。任期の向こう4年間、年に3回1カ月ずつジュネーブに滞在し、各国の報告書などをもとに条約履行状況を審査し、さらなる履行のために勧告する。一層多忙になるが、「本当にやりたいことの入口に立った」と、大谷は自らを奮い立たせているところだ。
世界では児童兵士の問題や、移民問題などが緊急の課題になっています。日本でもいじめ苦による自殺や、性的搾取などの問題がありますが、世界のなかで相対的に見れば人権は守られていると思います。でも、日本で起きている子どもの問題は社会問題として捉えられても、子どもの人権問題だと受け止められていません。もっと社会の関心を喚起する必要がありますし、私はジュネーブ滞在期間以外でも委員として、国内外にわたっての条約推進に全力を傾けたいと考えています。そして、いずれ委員が終わっても、「弁護士業に戻ります」ではなく、より国際的な活動のほうにシフトしていきたいですね。具体的にはまだわかりませんが、私にとっては今が“入口”、さらに先に進みたいのです。
抱き続けてきた思いが変わらないんですよ。弁護士の仕事に何ら不満はなく、むしろやればやるほど、奥の深さややりがいを感じます。それでも、自分の臆病な気持ちと闘いながら、「行きたい世界」に気持ちが向く。時々「そんなしんどい努力をしなくても」って思うんですけど、最後は「どうしてもやりたい」になっちゃう(笑)。
私が、特に若い人たちに伝えたいのは、やりたいことがあったら、遠慮しないで声に出すべきだということ。日本人って、「頑張っていれば誰かが見てくれている」と思う傾向があるでしょ。ギラギラした野心的な感じって好まれないけれど、それは少なくとも、国際社会で活躍したいと思っている場合には通用しません。
私自身、いろんなチャンスを与えられたり、引き上げてもらったりしてきたのは、「これをやりたい」とはっきり表明してきたからです。人との出会いも含めて、これまでにいただいた支援はきっと偶然ではないはず。人に伝え、努力をしてきたから今日がある、それが偽らざる実感です。どの分野であれ、本当にやりたいこと、自分の探し物が見つかったら、そこに対する思いを大切に、ずっと持ち続けてほしいと思います。
※本文中敬称略









