第1 正義
私は、法律ということが好きではなかった。法学部を選んだのも、消極的な理由だった。弁護士になりたいと思ったわけでもなければ、裁判官になりたいと思ったわけでもなければ、検事になりたいと思ったわけでもない。法律学には何の興味もなかった。法律学は、およそ学問とは言えない、という思いだった。
数学に対する尊敬が小学校以来50有余年あった。たった1人の人間が数学上の真理を発見したとしよう。その1人は、論理でもって、地球上に存在した全ての他人を説得することができる。ところが、法律は、○○説というように、1つの説が他の説を説得することはできない。論理性だけで勝負がつかないということが、法律学が魅力のない理由だった。私は、数学をやれなかった劣等感をずっと引きずっていた。
それが5年前、59歳のときに、ある日突然、自分の頭上の霧が晴れ、紺碧の空が広がったように感じた。その時、自らの背中に白刃が当てられたかのごとき「衝撃」を受けたことを、今でもハッキリ思い出す。「人間にとってもう1つ大事なことがある。それは正義である」と。「正義」という言葉は、とても青臭くて、それまで人前ではとても言えない言葉だった。しかし、その時、「正義」ということが、人間にとって、数学の論理性と並んで、もう1つの重要なことだと思い至った。
人間の営みの中には、数学的な処理、論理性の貫徹のみでは、解決できないことがある。その場で機能しなければならないのが正義である。人間は、正義に適って生きなければ、生きる意味がない。
正義には2つの意味がある。絶対的な正義と相対的な正義。正義の概念を絶対的な正義の意味に捉えてしまうと、これはもう宗教、政治の世界に迷い込んでしまう。例えば、キリスト教が正義なのか、イスラム教が正義なのか、あるいはイラク戦争が正義なのか、第2次世界大戦が果たして正義だったのか、ガリレオの宗教裁判のごとく天動説が正しいのか、地動説が正しいのか、という問題である。これらの問題は、全員が共有できる正義はない。
ただ、裁判で争われる正義は、初歩的な正義である。原告の主張する正義と被告の主張する正義とを比べて、どちらがより正義かということである。
私は、裁判で問われる正義は3つに絞ってよいと思う。
1つは、「自分が得をして相手が損をするような出来事について嘘をつかないこと」と「それについて嘘をつくこと」の両方を比べて、どちらが相対的に正義かという問題である。
例えば、新聞報道が真実であるとすれば、UFJは、金融庁から捜査を受けて証拠隠滅をした。新聞報道が真実であるとすれば、防衛庁の談合事件の場合も、ライブドア事件の場合も、関係者は嘘をついている。「相手に損をさせて自分が得をするような嘘をつくこと」は、「それについて嘘をつかないこと」と比べれば、不正義である。相手を敗訴させようとの目的を持って法廷で嘘をつくことはよくないことである。正義の観点から法令を解釈して得た法を真実に対して適用して、正義を実現することが裁判である。真実が裁判の前提である。嘘は真実に矛盾する。法廷では、嘘は不正義である。
2つは、契約を守ることと守らないことと比べてみれば、契約を守るほうが契約を守らないよりも正義である。約350年前のイギリスの哲学者・トーマス・ホッブスは、「リヴァイアサン」(1651)という書物の中で、「正義とは契約を守ることである」と言い切っている。対等な立場で結んだ契約でありながら、当事者が契約を守らないことは不正義である。あるいは弱者と強者が契約を締結しながら、強者が契約を守らないことは、正義に反する。
3つは、違法な行為をすることと適法な行為をすることを比べれば、適法な行為のほうが、違法な行為より、より正義である。裁判上問われている正義というのは、この3つに絞るべきである。
正義とは何ぞやという議論をしだすと100人が100人の正義があるという議論が出てこよう。しかしながら、裁判で争われる、法律家の踏ん張りどころの正義というのは、この3つに限定してよいと考える。裁判上の正義の概念をあまり広げてしまうと、結局は説得力を欠いてしまうからである。
第2 裁判所による法の創造

裁判をどう捉えるかということについて、2つの考え方がある。1つは、裁判は、法令を正義と憲法に基づいて解釈して、真実にこれを適用して正義を実現することであるという考え方である。これに対して、裁判は、当事者の利害を調整する場であるというもう1つの考え方がある。裁判とは、原告の利益と被告の利益を考量することによって落としどころを探る場であるという考え方である。たしかに、白か黒という決着の仕方が常に人間社会の争いの解決の仕方に合っているかというと、そうではないであろう。グレーの決着のほうが白か黒かの決着より、当事者にとっては納得のいく紛争解決方法である場合が多々あるであろう。実際の裁判でも、和解という決着が相当大きな比重を占めている。ただ、全部が全部グレーの解決でいいのか、それが果たして裁判所の目指す理想の紛争解決方法かというと、私はそうでないと思う。
裁判所は、法を創造するという機能を持っている。そこで1つ1つ和解によって解決して、当事者限りで紛争を閉じてしまい、紛争の内容も公開しないということになると、裁判所は、ルールメーカとして、機能しないことになる。裁判所が法を創造するという重大な使命に直面したときは、裁判所が逃げることなく規範を作っていくべきであろう。「調停事件の処理の仕方、和解の決着こそが、裁判の理想だ」という考え方は、大岡裁きに見られるように、日本では長い伝統のある考え方であろう。しかしながら、法廷は、真実に法を適用して正義を実現する場である。ある裁判例が、1つの裁判所だけではなく、他の多くの裁判所によっても一貫して肯認されるとなると、その裁判例は、法として固まっていくことになる。判例によってルールが創造されることは、積極的に認められるべきである。
1588年にアングロサクソンの国・イギリスはスペインの無敵艦隊をドーバー海峡で破った。英国は、この海戦以来、第1次世界大戦前まで、海軍力ナンバーワンの地位を他国と並んだことはあっても他国には譲っていない。そして英国の判例法を承継しているアメリカも、やはりアングロサクソンの国である。アメリカは、第1次世界大戦直前以降、現在まで、軍事力ナンバーワンの地位を他国に譲っていない。アングロサクソンは、織田信長の時代(1582年に本能寺の変で自害)に覇権をとってから現在まで、覇権を他国に譲っていない。
英国は、アヘン戦争で中国を屈服させた。アングロサクソンの英国は、インドのムガール帝国に勝利している。ナチス・ドイツに対しても、ソ連に対しても、アングロサクソンのアメリカは、勝利している。日本も、第2次世界大戦でアメリカに負けた。フランスも、イタリアも、第2次世界大戦でアメリカに解放された。では、アングロサクソンとそれ以外の国と何が違うのか。アングロサクソンは、芸術、文学、科学の分野で、歴史上の人物を輩出している。アイザック・ニュートンもイギリス人であるし、シェイクスピアもイギリス人である。産業革命もイギリスで起きている。たしかに飛び抜けて才能ある人たちがイギリスから出ていることは間違いない。しかし、モーツァルトは、アングロサクソンではないし、ミケランジェロも、違うし、アインシュタインも、そうではない。決してアングロサクソンだけが芸術、文学、科学の分野で飛び抜けているわけではない。
また、国土の広さ、資源の多さが、アメリカがナンバーワンである理由ではない。昔のソ連は、国土の広さ、資源の多さといった面では、アメリカに決して負けていなかった。それでも、アメリカに優越することはできなかった。
それでは、何故にアングロサクソンが過去400有余年にわたって、世界の覇権を他に流れないのかが、問われる。
アングロサクソンが司法国家であり、それ以外の国が行政国家であるということが、アングロサクソンが400年を超えて世界のナンバーワンであり続け、それ以外の国がナンバーワンになれない理由であろう。中国、ソ連、ドイツ、フランス、日本は、皆、官僚国家、すなわち、行政国家である。行政国家というのは、基本的には、国民にとってルールが必ずしも明らかでない。行政指導が大きな役割を果たしている。問題が起きたら、国民は、官僚に解決法を聞いて官僚の示す指導に従って問題を解決する。日本のつい最近までの大蔵行政、金融行政は、行政指導によって行政が行われ、ルールがはっきりしていなかった。税金においてもそうであった。官僚あるいは役所が「こうだ」と言うと、国民、企業は、それにおとなしく従うのみで、法律上の議論を組み立てて、裁判で国と争うということをしない。だから規範、すなわちルールが国民、企業の前に、明らかにならない。行政が事前規制をするので、国民、企業の間に競争が起こらない。業界の中に落伍者を出さないということは、生産が低く一番効率の悪い企業を市場から退場させないわけであるから、生産性が低く、効率の悪い企業の基準が、その業界の市場で生存し続くための基準となってしまう。競争しない産業は、競争をする産業と比べると、効率の点で劣ってしまう。
司法国家というのは、事前規制をしないで事後規制をするわけであるから、ルールを事前に国民の前に明らかにする。国民は、自己責任によって、自らの行為がそのルールに違反しているかどうかを判断する。企業は、ルール以外の規制、すなわち、行政指導を受けないで競争する。司法国家・アングロサクソン、すなわち、イギリス、アメリカと行政国家の、それぞれの400年の歴史が、司法国家の有用性と行政国家の非効率性を証明している、と言えよう。
第3 裁判にとっての真実発見の重要度
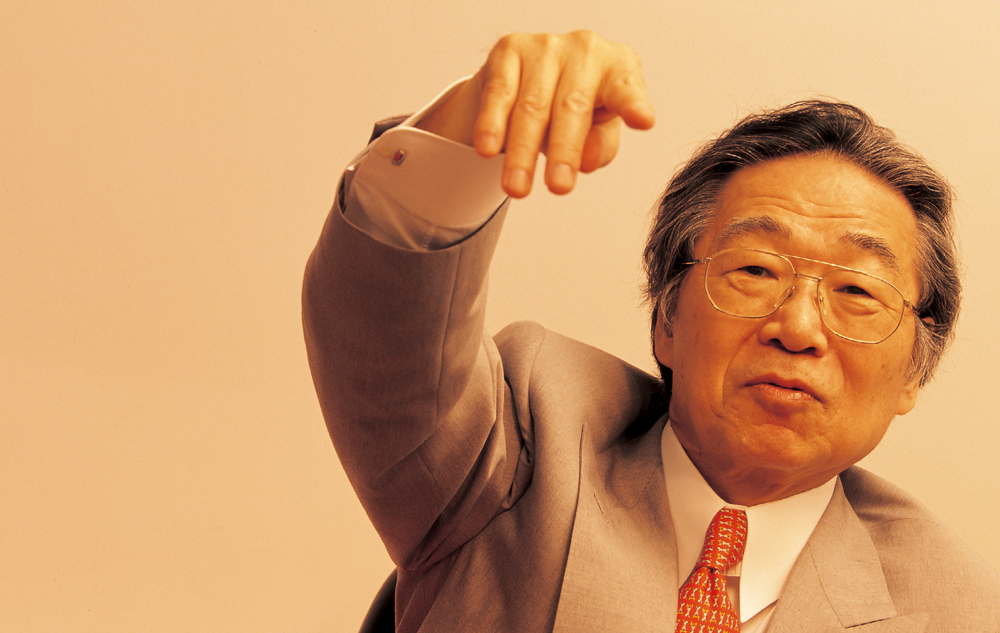
法曹に身を置く人、これから弁護士になろうとする人、すべてに「裁判上の正義」を日頃から「論点」として持っていてほしいと願う。法律は裁判あってのもので、裁判は司法という器あってのもの。真実に法を適用して正義を実現する。正義を論じ、正義を説くには、勇気と自信が必要です。自信は実績から作られますから、まずは一つでいい、自分が納得できる成功体験を得ることです。一つひとつ実績を積み重ねれば、今よりレベルは一つずつ上がる。すると、また新しいステージにトライできますから。
1978年、私がアメリカに留学して1カ月目くらいのとき、新聞の一面に大きな写真が出ていた。その写真は30代の男女の写真だったが、その記事を読んでみると、その男性は服役していた新聞記者で、女性はその妻、周りで祝福している多くの人たちは新聞記者仲間、写真をとった場所は刑務所の門の前と書いてあった。さらにもっと詳しく読み進むと、取材源の秘匿を理由に証言を拒否したその新聞記者を、裁判所が証言拒否の法廷侮辱罪で刑務所に入れたが、記者が刑期を終えて出所したので、妻、同僚が出所祝いをしているのだという記事であった。その記事を読んで、裁判所とジャーナリストの双方が、いずれも真実のために、法廷ですさまじい戦いをしていることを知った。裁判所は、真実に対し法を適用し、正義を実現するために、新聞記者に証言を求めた。しかし、ジャーナリストは、真実を報道して民主主義を実現するために取材源を秘匿した。新聞記者は、服役を覚悟で民主主義実現の前提となる真実を報道するために戦った。正義を実現するために法廷侮辱罪を宣告した裁判官も、万感の思いをもって彼を服役させたのであろう。あくまで真実を報道するために服役したジャーナリストも、万感の思いをもって刑務所に入ったことであろう。双方とも真実のために行動したのである。
ニューヨークタイムズ事件では、ブッシュ大統領の側近の国家機密の漏洩に関して、片方のジャーナリストは、取材源から証言していいという同意をもらって証言した。もう一人のジャーナリストは、取材源の秘匿を理由にして証言を拒否して、刑務所に入った。こういった真実に基づく証言を求める司法と真実の報道の目的のために取材源の秘匿を守り通そうとする報道機関のぶつかり合う法廷の場では、ジャーナリスト個人が取材源の秘匿のために刑務所に入っている。米国の裁判所にとっては、それほどまでに、法廷で真実を追究するという理念は譲れない理念なのであろう。日本の法律家は、司法にとって真実追究はどの程度必要なことなのか、という議論を真剣にすべきであろう。
それからもう1つ私が申し上げたいエピソードがある。もう10年ほど前になるが、カリフォルニアの連邦地裁で特許の裁判があった。私の依頼者は日本に所在する日本法人(被告)だったが、相手方米国法人(原告)から関係文書の文書提出命令(プロダクション・オブ・ドキュメンツ)の要求を受けた。段ボール箱を20~30箱、会社の大きな食堂にひろげて、ファイルに入っている関係書類を全部コピーしてはそのダンボールに次々と入れていった。ほとんどが日本語だが、最終的には4万枚くらいあったろうと思う。私の依頼者(法人)の1人の取締役が、争いとなっている商品について、世界中の特許侵害のおそれのある特許を記載した日本語の一覧表を作って、個人用にファイルして、会社に保管していた。その一覧表の中に相手方の特許が、1件記載されていた。それは具合が悪いことだった。というのは、メーカである被告が予め相手方の特許権に抵触することを知っていて、製品を米国に輸出したという事実の証拠になり得るからだ。この事実は、米国特許法上、特許権侵害者が損害金の3倍の賠償金を支払う義務を負う、という根拠にされ得る。私は、その取締役から「これは私が会社の業務と関係なく、個人的に作ったものなんで、出したくない」と相談を受けた。私も、相手方にこの文書を出したくないんで、何とか理由をつけて出さないようにしようと思って、同じく被告側の弁護団の一人である米国人弁護士・ロマリー弁護士に相談した。それまでは、私がその訴訟の日本側の主任弁護人で、依頼者も私の依頼者ということもあって、米国人弁護士であるロマリー弁護士は、その時まで一貫して私の言うことをよく聞いて、私を立ててくれていたが、ロマリー弁護士は、その時態度をガラリと変えて、私の腹の中を見透かしたのだろう、「相手方にそれを出す以外に、方法はない。法廷では、どんな不利な事実だろうと、それが事実であれば、それを隠すことは、許されない。法廷に出された真実の上に立ってクライアントのために全知全能を傾けて弁護することこそが、弁護士のプロとしての職責である。」と大きな声で私を恫喝するがごとく、言った。その瞬間、私は、ロマリー弁護士の声に毅然としたものを感じ、襟を正す思いをしたのだった。私は、已むを得ず、4万枚のうちのたった3ページなので、書類の山の中に紛らわせるようにして相手方に出した。私は、相手方の米国弁護士は、4万枚のコピーの山の中からその3枚の日本語の一覧表を到底見つけられないだろうと思っていた。しかし、6カ月後に相手方の弁護士は、英語の翻訳文を付けて、我々が提出したその日本語の3枚の一覧表を証拠として提出してきた。相手方弁護士は、私が不可能と思っていたことをやってのけたのだった。私は、とても4万枚もの量を翻訳するのは無理だと思っていたが、カリフォルニアは日本人留学生もいるし、そういう人たちを動員して数カ月でもって、関係あるものと関係ないものを振るい分けて、ポイントとなる書類の個所を翻訳するということが可能だったわけだ。
その中で私は2つのことを学んだ。1つは米国弁護士の倫理性の高さだ。弁護士にとって、依頼者の利益のために勝つことが目的であることは間違いない。だけれども、それには、一つの重要な条件がある。プロとしての弁護士に期待されていることは、あくまでも真実を土台にした上で、依頼者のために全知全能を傾けて最善の弁護をすることだということだ。
もう1つは、相手方の米国弁護士の真実発見にかける執念。アメリカのプロダクション・オブ・ドキュメンツと言おうか、デポジションと言おうか、証拠開示の徹底ぶり、双方の弁護士のそれに対するエネルギーの注ぎ方、真実発見のために行動する執念、これが判例法の国民が、裁判所が法を創造することを許容する根拠の1つだと思う。









