英語に興味を持ち、早くから国際的な仕事を志向する
半世紀以上にわたり法曹界で活躍してきた濱田邦夫の来歴は、振り返れば“初物尽くし”。国際金融法務の草分けとして同分野を牽引してきた濱田は、国際的証券発行など、国内初とされる案件を数々手がけてきた。そして、1980年代後半にはロンドン事務所を開設。これは、我が国の法律事務所としては第1号の海外事務所となった。また、種々の公職にも就いてきたなか、創立に尽力したIPBA(環太平洋法曹協会)では初代会長に就任。さらに64歳の時には、ビジネスロイヤーとして初めて最高裁判事に任官……と、まさに先陣を切り続けてきた。「ほかの人にはできないことを」という旺盛な開拓魂こそが、濱田の真骨頂である。
国際的な仕事をしたいと考えるようになったのは、生い立ちが影響していると思いますね。私は神戸で生まれたものの、会社員だった父の転勤に伴い、各地を転々としてきました。小学校だけで東京、静岡、新潟と3度転校し、その後、再度東京に移り住んで、ようやく落ち着いたのは高校生になった頃。ローカルな土地や人々と深いかかわりを持つことがなかったものだから、私には故郷という概念がないんですよ。土着性や地縁にとらわれない性分は、ここからきているのでしょう。
加えて、父からの影響もあります。東大工学部出のエンジニアだったんですけど、あまり世渡りがうまくないというか、日本的な付き合いを好まず、時として正論をはっきり口にする人だったんですね。だから私にも「世間的には、そんなことを言うものじゃない」などと諭したことはなく、私の思いや考えを尊重してくれた。時代的には、珍しい感覚だったように思います。
敗戦を迎えたのは9歳の時で、私は静岡にいたんですけど、ほどなくして、軍服に身を包んだ占領軍の姿を目にするようになりました。そんなある日、音楽好きな父が、英語で書かれたアメリカ歌謡の本を買ってきたのです。フォスターの『草競馬』などが載っている本でね、これが英語に興味を持つきっかけになった。もちろん愛国精神をたたき込まれていたから、アメリカに対する反発心はあったけれど、占領軍を介して英語の世界に接したことは、私に、広く外国への興味も抱かせたのです。高校生の頃には「英語を使って仕事してみたい」と思っていたので、英会話学校に通ったり、洋画の対訳や、当時のラジオ放送・FENを見聞きしながら積極的に英語に触れていました。

「あまり勉強した記憶がない」と言う濱田だが、進学校である日比谷高校を経て東京大学法学部に入学と、いわゆる秀才コースを歩んでいる。この頃に描いていた職業イメージは外交官。従前の濱田からすれば自然な流れである。その進路が変わったのは、名門法律サークル「東大法律相談所」での活動を通じ、法律家にも魅力を感じたからだ。
父は、最終的には意に反するかたちで会社を辞め、同様に会社勤めをしていた兄2人を見ていてもなかなか大変そうで、「宮仕えは自分に向かない」という思いもありました。サークルの活動は面白かったし、法律家は自分の足で立てる専門職でしょう、そこに大きく惹かれたわけです。司法試験を受けたのは4年生の時ですが、これが一発で運よく受かってしまった(笑)。私は、教科書主体の“通常の勉強”というものを、ほとんどしてこなかったんですよ。むしろ独学的だったし、何かを徹底的に勉強するというより、全体の概念や方向性を理解してポイントをつかむことのほうが得意で。それが、たまたま奏功したのかもしれません。
国際弁護士を目指すというのは、司法修習生の時から決めていました。当時、東大サークル出身の先輩の多くは、裁判官になる道を選ぶのが常で、私も指導判事から熱心に誘っていただいたのです。でも、仕事が堅苦しそうで、どうにも気が向かなかった。他方、弁護士修習では、かつて日弁連の会長も務められた渡部喜十郎先生にお世話になったんですけど、世間知らずの私に現実を見せようと思われたのか……けっこう泥くさい場面に付き合わされまして(笑)。ドメスティックな仕事は、自分には無理だなぁと。
そもそも外交官になりたかったわけですから、弁護士になるとすれば、やはり好きな英語を使える仕事がしたかった。もちろん、渉外弁護士の存在は圧倒的に少数だったし、「法廷に立たない渉外弁護士など真の弁護士にあらず」なんて揶揄されていた時代です。それでも、何か新しいことを、ほかの人にはできないことを、という思いが強かった。このスタンスは、以降もずっと変わっていませんね。
数少ない日本の渉外弁護士として、培ったスキルと矜持
濱田が最初に籍を置いたのは妹尾晃法律事務所である。きっかけは、司法研修所内に掲示されていた新人弁護士募集の張り紙で、そこにあったリチャード・ラビノウィッツ氏(当時の準会員弁護士)の名に惹かれてのことだ。ただ、時代を反映して経緯は少々複雑。募集自体はアンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(以下AMR)のものだったが、入所希望者に対する面接は、彼らからの信任が厚い妹尾弁護士が行っていたのである。
ほかの渉外事務所と比べると、初任給は格段に低かったんですよ。でも、その昔、法律雑誌で読んだラビノウィッツ先生の『日本の弁護士』という学位論文に関心があったので、冷やかし半分で訪問してみようかと。その時の条件が、「妹尾晃弁護士と面接すること」。私の前に、準会員の先生方と、彼らが直接雇用した新人弁護士との間に処遇上のトラブルがあったらしく、以降、妹尾先生は面接や新人育成を手助けしていたのです。先生は眼光鋭い方でね、面接で一瞬にして射すくめられた私は、その場で入所を決めていました。「まずは私のところでやれ」という言葉に、「はい」って即答ですよ。
渉外法律事務を志すなら、当初数年間は一般の民事・刑事事件も経験したほうがいいということ。そして、外国人である準会員とどう向き合えばいいかを、先生はご自身の経験に則って教えてくださった。妹尾晃法律事務所での在籍は2年と短かったけれど、私はここで、弁護士としての基礎と心構えをたたき込んでもらったのです。何より、「日本の弁護士の独立を目指す」という私の基本姿勢が確立された。今の時代ではピンとこないでしょうが、敗戦直後の混乱期は、日本の法曹もまた占領下に置かれていたわけです。そのなかで、常に日本人弁護士として毅然とした態度を貫かれてきた妹尾先生との出会いは、とても大きなものでした。
通常の民事や刑事事件をある程度経験し、AMRに移籍してからは、本格的に渉外法律事務に携わるようになりました。当初の主な仕事は、外国企業からの日本への資本導入や技術提携サポートで、時間に追われながらも、新しいことを知る日々は面白かったですねぇ。なかでもラビノウィッツ先生には、仕事のことだけでなく、外国の依頼者たちとの社交の仕方も教わるなど、ずいぶんお世話になったものです。

渉外弁護士として基礎トレーニングを積み、66年には、ハーバード大学ロースクール修士課程を修了。培ったグローバルな視野のもと、濱田は、ことキャピタル・マーケットの分野において力を発揮するようになる。60年代に開始された、日本企業によるユーロドル建て転換社債など、海外市場における証券発行の“はしり案件”にも多く関与してきた。そして34歳でAMRの名目パートナーに就任。と、ここまでは順風だったが……2年後には「AMRを辞める羽目に陥った」のである。
袂を分かつ直接的なきっかけになったのは、71年に受任した、シンガポール開発銀行によるアジアドル債発行案件です。これは、大和証券が日本で初めて国際的な債券発行の引受主幹事を務めたもので、私はそのリーガル・アドバイザーとして入りました。この時、AMRの実質パートナーの準会員たちと、私の主張が対立したんですよ。
彼らの主張としてはこうです。シンガポール会社法の祖はイギリスから来ているから、「自分たちの職務範囲にある」と。つまり「英米国法に関する法律事務に入る」というわけです。でも、独立国であるシンガポールには独自の会社法があるわけで、英米国法のそれとは異なる。私は、準会員たちに「この案件には関与できないはずだ」と強く主張し、実際に排除したのです。案件自体は成功しましたが、彼らには面白くない話だったでしょう。
実は、その前にも伏線があったのです。朝日新聞に取材された際、私は「我が国の渉外法律事務は、いずれ日本の弁護士が、外国人弁護士準会員たちをリプレイスして行うようになるだろう」というコメントを出したんですね。特に他意はなかったのですが、この“リプレイス”という言葉は強く、「俺たち正会員が取って代わる」みたいな出方になってしまった。準会員たちにすれば“やばい”。まぁ若気の至りもあったけれど、でも私には、日本の弁護士として譲れない矜持もあったのです。
これら私の言動が恐れを招いたのか、目前に控えていた実質パートナーへの道は閉ざされてしまった。「君をパートナーにするつもりはない。今の身分のままなら事務所に残ってもいいが」。そんな仰天かつ屈辱的な宣告を受けたら、居残るわけにいかないでしょう。それまでの10年間、ずいぶんお世話になりましたが、結局、私は事務所を辞める決断をしたのです。
国際金融法務における先鋒として、国内外を駆け抜けた日々

何か新しいことを、自分にしかできないことを。私には、ずっとそういう思いがある
“宣告”は急だったから、濱田には何の準備もなかった。行き場を求めていたところ、パートナーとして迎え入れてくれたのが、かつて留学先で共に学んだ柳田幸男弁護士である。同氏の事務所名を「柳田濱田法律事務所(英語名:Hamada&Yanagida)」に改称し、再スタートを切ったのは72年。規模は小さかったが、新しい事務所でも国際的な案件を数々手がけた。そして、のちに生涯の盟友となる松本啓二弁護士と出会ったのも、この時代であった。
日本市場での外国株式の公募案件を手がけていたのですが、そのなかの一つ、アメリカの大手通信会社・GTE社の案件で、現地での調査業務に協力してくれたのが松本弁護士。これを機に彼もHamada&Yanagidaに加わり、事務所も順当に成長していきました。ですが2年ほど経った頃、柳田弁護士と経営方針が合わなくなり、パートナーシップは解消。その後、新たに立ち上げたのが「濱田松本法律事務所」です。この事務所は、2002年に森綜合法律事務所と合併するのですが、それまでの27年間は、わりに名の通った渉外事務所として走り続けることになります。
「日本の弁護士の手で世界に通用する法律事務所をつくる」という意気込みは、設立当初からありました。実際、中心業務は国際的証券発行や金融案件、ベンチャーキャピタルの組成などといったもので、純国内案件はほとんどなかったですから。大きなチャレンジとなったのは、87年のロンドン事務所開設。日本の法律事務所としては、初の海外事務所です。この頃、日本企業はヨーロッパにもどんどん進出していた時代で、我々には、その事業活動に伴って必要となる法的サービスを、自国の弁護士として、かつ現地でサポートしたいという思いがあったのです。
しかしながら、事務所開設直後に起きたブラック・マンデーは乗り切ったものの、国際金融市場の様変わり、日本のバブル経済終焉という逆風を受け、事務所は7年間の苦闘の末に、ロンドンから撤退せざるを得ませんでした。一因には、「自国弁護士を利用する」ということに、日本の企業や政府が積極的でなかったこともある。欧米の企業は、世界のどこでも自国の弁護士をパートナーとして起用するんですけどね。「海外で日本の弁護士は役に立たない」という思い込みは、日本の渉外法務の一つ問題点でもあると思う。
90年代に入ると、国際金融市場の変質と相まって、事務所の業務も様変わりしてきた。M&Aや市場経済化支援、不良債券の流動化、証券化案件など、その幅は、国内の案件も含めて著しく広がった。なかでも、濱田が最高裁に入る前の数年間は、大型金融機関の倒産事件に多く関与してきたという。
95年のベアリング証券特別清算事件で、清算人を務めたことが端緒となり、国際的な企業倒産事件にかかわるようになりました。いろいろな事情も加わって、大型倒産案件に関与するようになったんですけど、従前畑違いだった私が、この領域に入ってきたことは、いわゆる倒産弁護士の間ではけっこう話題になったらしい。幸い、文句は言われませんでしたけどね(笑)。
印象的な一件があったのは、山一證券です。当初、山一證券は極度の混乱状態に陥り、事務所もどこが入るか全然わからないような状況でした。まぁ紆余曲折あって、私たちが国際面での任意整理をすることになったのですが、その時、イギリスの某巨大事務所が訪ねてきたのです。何の話かと思ったら、「山一の案件をやると聞いたが、君たちでは無理だろう。うちでやってあげるよ」と言う。これには、カチンときましたねぇ。遡れば、幼き日に占領軍に対して決して「ギブ・ミー・チョコレート」とは言わなかった精神が、私にはずっとあるんですよ。
IPBAの設立においても、根っこにあったのは、日本の弁護士の国際的な活躍を願う気持ちです。私はIBA(国際法曹協会)にも参加してきましたが、やはり欧米中心で、アジアから参加する弁護士にしても、出てくるのは地元の大変な成功者ばかり。それでは面白くないし、IBAに埋没しない組織をつくろうと、三宅能生弁護士ほか関係者たちと動いたわけです。IPBAの要職には多くの日本人が就任してきたし、数ある国際的な法曹組織のなかでも、日本人が設立と発展に大きく寄与したという点において、意義は深い。創立から25年経ちますが、ずっと日本に事務局を置き、力ある法曹協会に育ってきたことは、初代会長として誇りに思っています。
自由で、平和な美しい日本を守るために。提言と行動に立つ
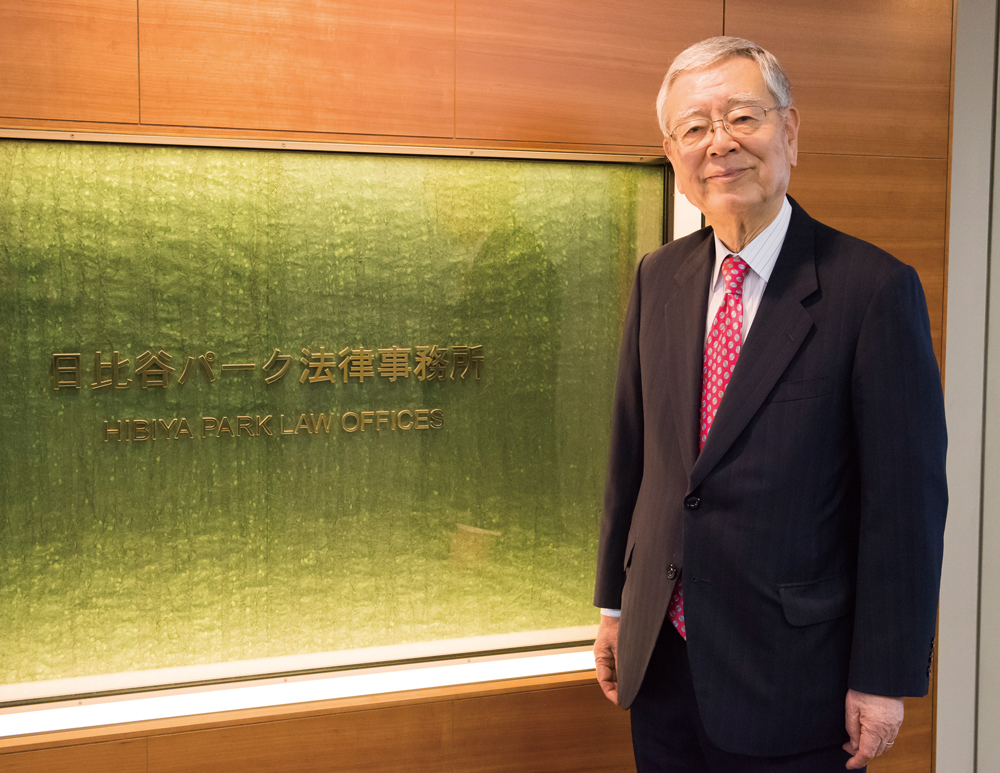
01年、濱田は最高裁判事に任官した。当時の小泉内閣によって任命されたものだが、本人にすれば「青天の霹靂」。世界的に見ても、ビジネスロイヤーが自国の最高裁判事になることは希有である。日本経済が沈み、グローバリゼーションの大波に対処する必要に迫られていたこの時代、「国際派としての経歴を持つ私に、たまたま白羽の矢が立ったのでしょう」。
正真正銘の「びっくり」です。でも、緊張や迷いというよりは、感覚としては好奇心のほうが強かった。まず、何より驚いたのは、裁判官が審理する膨大な事件の数です。5年間の任期中には、ロス疑惑や東電OL殺人事件などといった著名事件も担当しましたが、小法廷で関与した上告・上告受理申立事件や、特別上告などを合わせると、関与した事件数は優に1万件を超える。これは、信じがたい数ですよ。行政庁の大臣並みとされるでかい部屋に、ポツンと一人閉じ込められ、文字どおり山のような供述調書や報告書を次から次へと読んでいく。訴訟事件にほとんど接してこなかった私には、心身共に、なかなかこたえる仕事でした。
海外の上告制度の運営に学んで、日本でも審議事件をさらに絞り込み、加えて審理期間も短縮すべきではないか。あるいは、日本の裁判は口頭主義だというけれど、実際は、訴状や陳述を読み上げるだけという場が多く、口頭弁論といっても形式的すぎやしないか。などといった具合に、私は「おかしい」と思ったことには、あれこれ進言してきたつもりです。ビジネスロイヤーですからね、いわば最高裁判所という企業に“社外取締役”として入ったような心持ちだったのです。
そもそも、裁判所は国民の税金で運営されているサービス機関なのだから、一般社会にも、そして国際的にももっと通用する開かれた場であるべきです。という調子なものだから、事務局からは「濱田は扱いにくい」と思われたでしょうが、少しは改善されたこともあります。十のうち一つできたかどうか……ですけど、それなりにインパクトを残せたのではないかと思っています。
現在は、客員弁護士として日比谷パーク法律事務所に在籍。企業の社外役員、企業不祥事に関する第三者委員会などの仕事を中心にしながら、他方では、裁判員経験者の心のケアの問題を扱う任意団体や、再生エネルギーの普及を目的に活動する非営利団体などでも要職に就く。変わらず多忙な日々だ。法曹として何ができるか、何をすべきか、濱田は常に“今”を生きている。
昨年、「自由で、平和な美しい日本を守ろう!」という言葉で始まるマニフェスト、個人的な闘争宣言を出しました。最近の我が国の政治状況は、人間の自由と尊厳をないがしろにするような事態に立ち至っているわけで、一個人としても、法律家としても看過できません。例えば、自民党と公明党によって強行採決された一連の安全保障法制、あるいは昨今、憲法に入れろと言っている緊急事態条項。戦争や災害が起きた場合に、首相に権限を集中させるというこの条項は、基本的人権を過度に侵害する危険性があり、何より、憲法改正に対する国民のアレルギーを排することを狙ったものに過ぎません。
憲法の問題については、私は「絶対に変えるな」と思っているわけではないんです。ただ、過去70年間かけて日本が築き上げてきた自由で豊かな社会は、世界的に見ても大変貴重なもので、その礎となる憲法を変えるのならば、十二分な議論を重ねるべきです。戦後からの新憲法のもとで、自由な民主主義社会を生きてきた私には、その素晴らしさを次代に伝える義務があると思うから、黙っていられないのです。
震災復興、エネルギー、超高齢化など、日本には取り組むべき問題が様々あるわけです。日本という国がどうやって世界のなかで生き延び、そしてどう貢献していくか、私たちは、そこにもっと目を向けないといけない。法曹って、非常に大きな可能性を持つ世界でしょう。自分の信念をしっかり持ったうえで問題に臨めば、人や社会に貢献するような働きが必ずできるんですよ。「こんなものだ」と思ってはダメです。好奇心を失わず、どうすればいいのかを絶えず考え、法律という一つの武器を使いながら自分の生きざまを描いていってほしい。これが、若い法曹に向けた私からのメッセージです。「言うべき時に言うべきことを言う」「行うべき時に行うべきを行う」。ぜひ、そんな勇気を持ちながら……。
※本文中敬称略









