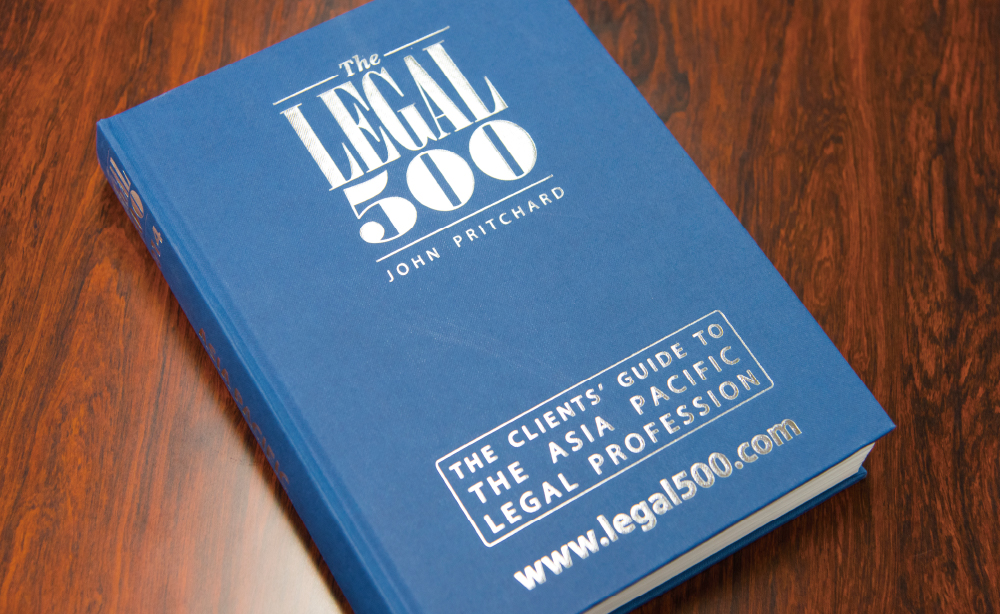前列左より、相澤貞止弁護士(42期)、左合輝行弁護士(56期)、山口修司弁護士(34期)、戸塚健彦弁護士(43期)
後列左より、赤塚寛弁護士(新62期)、津田勝也弁護士(60期)、髙野真一弁護士(新63期)、本郷隆弁護士(新66期)、岡部博記弁護士(31期)
前列左より、相澤貞止弁護士(42期)、左合輝行弁護士(56期)、山口修司弁護士(34期)、戸塚健彦弁護士(43期)
後列左より、赤塚寛弁護士(新62期)、津田勝也弁護士(60期)、髙野真一弁護士(新63期)、本郷隆弁護士(新66期)、岡部博記弁護士(31期)
STYLE OF WORK 事務所探訪
#76