母親に刷り込まれた目標叶え、東大法学部に。在学中に司法試験合格
渉外事務所所属の弁護士として北京に渡ったのは、中国の「弁護士業界」がまだ草創期にあった1994年暮れのことだった。現地で日本人ビジネスロイヤーのパイオニアの一人として奮闘した曾我貴志は、帰国後そこで得た経験、人脈という強みを生かし、活躍の場を広げていく。2012年には曽我法律事務所を立ち上げ、中国に留まらずアジア、さらには世界を対象にしたビジネスを展開中だ。ただし、現状は「狙ったのではなく結果」だとあえて言う。そこには、どんな“人生のターニングポイント”があったのか。
65年、川崎市多摩区の生まれです。川崎といっても海側から離れた丘陵地帯で、山あり川あり。そんな環境で、クワガタやザリガニ取りに夢中になるような子供時代を過ごしました。
親父は「出世はいいから、遠隔地への転勤は勘弁」という、“モーレツ社員”全盛の当時としては珍しい“ゆとり”型の銀行員。対して母親はまさに“昭和の母”で、「日本で偉くなるためには、いい大学に行かないとね」と長男を繰り返し諭すわけです。具体的には「東大法学部に行け」と(笑)。そんな話を聞かされているうちにすっかり洗脳され、小学5年になると自分から言い出して、週6日の塾通いもしました。
そういう流れで受験して、中高一貫の駒場東邦に進学したのです。中学では野球に打ち込み、高校では麻雀にハマったことも。でも東大受験という目標がありましたから、高1の終わり頃からは相当真剣に勉強したと思います。
東大文一の合格発表の日、珍しく親父が「一緒に見に行く」と言うのです。自分の番号を見つけた時は嬉しかった。自分のことよりも、そんな両親に親孝行ができたわけだから。

東大は最初の2年間を教養学部のある駒場キャンパスで過ごす。駒場には、難関を突破した安堵感からか“浮かれた空気”も漂う。「法学部に行くのだから司法試験の勉強をしよう」と教科書を揃え、予備校のガイダンスに顔を出したりもした曾我だったのだが……。
なぜ司法試験を考えたか?とにかく「最も難しい資格試験」にトライしてやろうという気持ちですね。法曹資格は持っておいたほうがいいだろうとも思っていました。ところが教科書を眺めてみると、やるべきことがたくさんある。とても片手間で対応できるような挑戦ではないことを認識させられ、気持ちは一気に萎えてしまいました。
そうなると、ますます駒場の緩んだ空気に抗いがたく、飲み歩いたりテニスのサークル活動に興じたり。気づけば普通の大学生をしていました(笑)。
このままではダメだと危機感を抱いたのは2年の夏のこと。そして思い立ったのが語学留学でした。中学時代から英語好きでしたので、本場で磨きをかけるのも悪くないと考えたのです。
初めての海外、行き先はロンドンです。ホームステイして語学学校に通いました。日本の英語教育も捨てたものじゃないと感じたのは、ペーパーテストでは高得点が取れること。その結果、一番レベルの高いクラスに振り分けられ、見回したら全員がヨーロッパ人。おかげで話し、聞くことは苦労しましたけれど、そのうちに友人もできました。そうなると毎日が楽しくて、「自分は国際舞台でやれるのではないか」という自信のようなものが沸き上がってきて。何よりも、「頑張ろう」と前向きな気持ちになれたのが大きかった。
帰国すると、ちょうど秋から法学部の授業が始まったところでした。“やる気モード”そのままに教科書を読んでみると、不思議なことに、1年生の時にちょっとかじっただけで書架の肥やしとしたはずなのに、これならやれるのではないか、と。ロンドンが私をアグレッシブに変えたのでした。
3年生になって本郷キャンパスに移る直前、実家を出て教室から歩いて2分の“貸間”に下宿しました。本気で司法試験を目指すための選択です。そこからの約2カ月が、今までの人生で最も勉強した時期と言っていいでしょうね。寝食も惜しんで……というか、貧乏生活で食のほうは黙っていても不自由でしたけど(笑)。
勉強は、ひたすら本を読む。眠い目をこすりながら授業に出るよりよほど効率的というのが、私の考えだったのです。ゼミ以外の授業の出席率は、半分くらいでしたね。結果3年生の5月にあった択一試験にパス、翌年首尾よく最終合格することができました。
渉外事務所に入所。NY、香港、そして中国へ
大学在学中に司法試験に合格した曾我は、卒業後に司法修習生となる。判事、検事、弁護士の仕事を実体験しつつ“職業選択”を行うわけだが、実は修習前、弁護士になるつもりはなかったのだという。
ここでも母親の言葉に引っ張られるわけですね。「年金もないような不安定な弁護士に最初からなる必要はないのでは」と(笑)。それもそうかなあ、という感じ。でも最初の実務修習でお世話になった柳田幸男先生の事務所で意識変革させられました。英語を使いたかったので渉外法律事務所での研修を希望し、東京弁護士会から柳田先生の事務所での修習の機会を与えていただいたのです。
この機会が私の運命を大きく変えました。柳田先生の仕事ぶりに触れるたび「企業のために戦っているのだ」という気迫みたいなものが、ビンビン伝わってくる。それでいて、働き方の自由度が高い。得意の語学力が武器になることもわかりました。それに比べると、裁判所の厳かな雰囲気は、どうも自分には合わない(笑)。検察も組織が大きすぎて自分には上手くやれないのではないかといった印象でした。
結果的に、司法修習を通じて「目指すべきは弁護士」「就職先は英語力を生かせる渉外弁護士事務所」という進路に定まっていったわけです。もし柳田先生の下で研修させていただけなかったら、今頃粛々と判決を書いていたかもしれず、それはそれでいい人生であったかもと思うこともありますが。
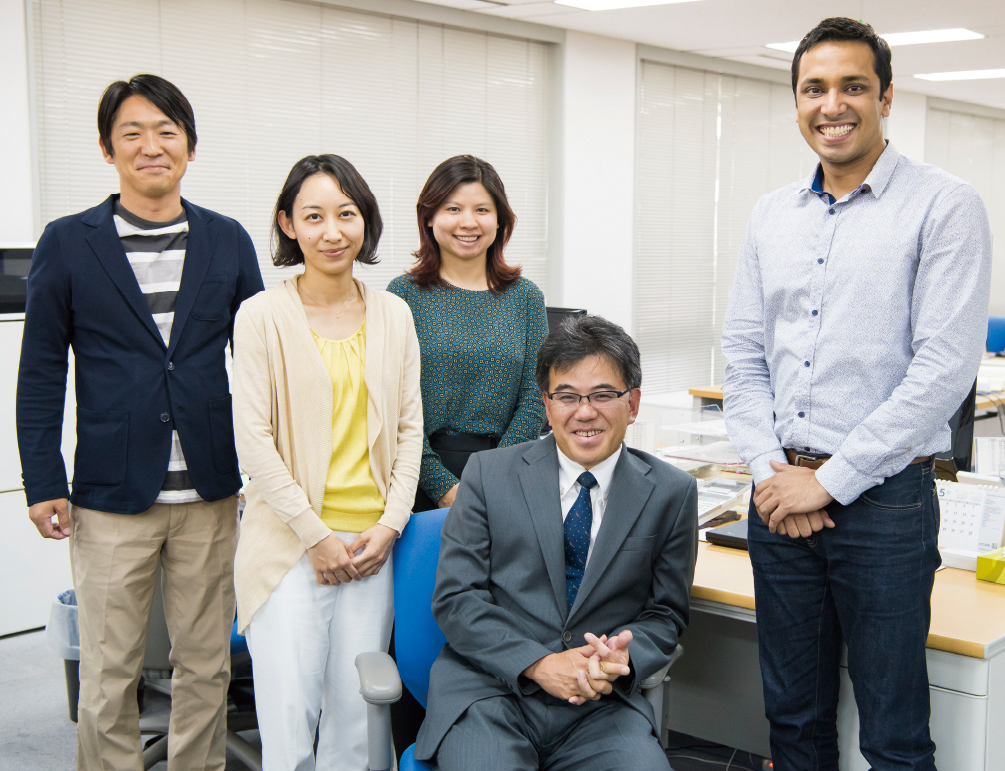
修習を終えた90年に入所したのは、アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所です。外国人が多くいて英語を使う環境に最も恵まれていそうだということと、早めに留学させてくれるのではないかという期待があったから。ロンドンの思い出もあって、早く留学したかったのです。当時のアンダーソンは、いい意味でバラバラ。いろんなタイプのパートナーが群雄割拠している感じ。仕事の中身も、若手には、外債発行、東証上場、リースといったファイナンスはもとより、外国の顧客向けの日本法のオピニオン、ジェネラルコーポレート、さらには訴訟、それも破産申立から民事執行、通常訴訟も全部やらせる、という感じでした。
当時は弁護士40人くらいの規模ですから、丁稚の私にも無秩序にアサインメントがくるわけですよ。睡眠時間を削ればいくらでも仕事はできるというノリで、片端から受けました。奉公に入ったその日から、野菜の皮むきだけではなく、皿洗いもやればモップがけや下ごしらえも、場合によっては仕上げや接客も。そうやって、知らず知らず幅広い仕事のノウハウを蓄積できたという意味で得難い経験でした。パートナーの流儀も様々で、「後は任せたよ」と放任型の先生もいれば、苦労して書いた訴状を読めないくらい真っ赤に手直しする先生も。だから、ある程度主体性を持った仕事から完全な下働きまで、仕事の性質という点でも多様な体験をさせてもらった気がします。
念願の留学を認められるのは、そんな“丁稚奉公”を2年あまり務めた92年のことだった。米国ミシガン大学ロースクールに学び、ニューヨークのローファームで研修、同州弁護士資格も取得した。と、ここまでは、渉外事務所の弁護士ならば一般的な道のりといってもいい。ところが曾我は、「プラスαのつもりで」別の研修希望を申し出ていた。それが、彼曰く「人生の第2ステージ」の幕を上げることになるなどとはつゆ知らず、である。
私は少し早めに外に出してもらったのだし、ニューヨークだけではなくて、アジアの金融マーケット、具体的には香港も見てみたいと思ったのです。そこで上司に相談したら、当時アンダーソンにいた香港弁護士のつてで、現地の事務所を紹介してもらえることに。ところが、本当の“プラスα”はその先でした。上司は、「どうせ香港に行くのだったら、中国本土に渡って中国語を習得してこい」と言う。後先考えず、「はい」と即答していました。外国語をもう一つものにするチャンス到来、くらいの気持ちです。
それにしても、なぜ上司がそんなことを言ったのか?当時、アジア企業の東証への上場が始まっていました。実際にマレーシアや香港の不動産会社などが上場を果たしたのですが、アンダーソンはそれらの企業の顧問になっていたのです。で、次は間違いなく中国だろう、と。そうすると、必然的に中国語が話せて現地の事情にも詳しい弁護士が必要になる。そんなタイミングで、突然「香港に行きたい」と手を挙げた奴がいた、というわけ(笑)。結局、アメリカには2年、その後渡った香港には4カ月いて、94年の暮れも押し詰まった頃、私は極寒の北京の地を踏んだのです。
中国人と親交を深め、現地事務所開設に奔走。ノウハウを蓄える

人生で二度感じた“追い込まれ感”。そのたびに秘めた力が発揮された
寒さは気候だけではなかった。語学習得はいいが、生活費も含めて事務所からの援助はゼロ。1年間の約束で妻子を自分の実家に預けて扶養義務を放棄し、父親から100万円を借り、1日“食費500円”で過ごす日々が始まった。そんな状況で1日6時間の家庭教師をつけ、さらに10時間の独学。猛勉強なのは確かだが、それで「『ニーハオ』から始めて、2カ月でけっこうペラペラになった」というから、やはりただものではない。
ある日ふと「あれ、この“追い込まれ感”は経験があるぞ」と思ったのです。そう、本気で司法試験に挑もうと決めて、本郷で下宿を始めた頃の貧乏生活と似ていた。あの時も「やるしかない」と覚悟を決めて勉強した結果、数カ月後に択一に合格できた。そう考えると、人間、秘めたるエネルギーを発揮するには多少追い詰められたほうがいいのかな、という気もします。中国語が話せるようになると一気に世界が広がりました。買い物にもカラオケにも行ける(笑)。
そのうちアンダーソンからのミッションも届きました。当時、先ほどお話しした東証上場を狙う中国企業は2社。そこに交互に通っては、交流するのです。今は違いますけど、あの頃の国有企業の人たちは、煙草スパスパ、酒は水のごとくという感じで自分には妙に合っていました。アンダーソンから案件を抱えてくる先生の通訳も重要な仕事でした。とはいえ普通の通訳と違って法律の知識が必要になる。だから重宝もされたし、自分自身の勉強にもなりました。結局上場自体は、東京マーケットの事情で挫折したのですが、私にとってみれば、中国人とベタなつき合いを重ねたあの時期が、今の仕事の礎を築くことになったのです。
そんなミッションと同時並行で進めていたのが、アンダーソンの北京事務所開設に向けた準備である。司法部との折衝などを進め、設立にこぎつけたのは98年。曾我はパートナー・所長として、派遣されていた2人の弁護士を指導する立場となる。この頃、中国ビジネスの潮目も変わりつつあった。
中国企業の東証上場がダメになったのと入れ替わるように、日本企業の中国進出にかかわる仕事が急増したのです。合弁契約作成、債権回収の依頼や「トラブルで撤退するから交渉に同席してほしい」といった話も多かった。シンジケートローンやプロジェクトファイナンス的な事案にかかわることもありました。実はそこで生きたのが、新人時代の“丁稚奉公”です。とにかく多種多様な案件が舞い込んでくるのですが、とりあえず「こいつ何もわかってないな」と思われない程度の対応ができたのは、あの経験があったからです。断らずに仕事してよかったなと、つくづく思いました。
ある運命的な出会いがあったのは、99年のこと。商務省、日本でいえば経産省を辞めた孟さんという若い人物が、突然訪ねてきたのです。そして「これから日中の貿易摩擦が激しさを増すだろうから、その対応へのニーズが高まる。一緒に日本のビジネスを開拓しないか」と言うのです。北京にいると、外国人弁護士へのこの手の接触は日常茶飯事ですから、その時は半信半疑のままお引き取り願ったのですが……。数カ月後、なんと中国政府が日本の化学メーカー数社に対し、アンチダンピングの調査を開始、そのうちの1社から「弁護士を探している」と連絡が入ったのです。慌てて、しまっていた彼の名刺を取り出し、会って話しました。彼は関連立法に携わった人で、商務省の調査官との信頼関係も厚い、またとないパートナーでした。孟さんの見立てどおり、その後も対日ダンピング提訴は多発。そんな中、彼と組むことで、依頼を受けたお客さまには、望ましい結果を提供し続けることができた。通商分野は、今でも我々の業務の柱の一つとなっています。すべてはあの時の“1枚の名刺”が出発点でした。
結局、中国には約6年いました。その頃の中国は弁護士制度自体が草創期で、日本人弁護士には市場開拓の大きなチャンスが広がっていることを実感したものです。時移り、今では中国弁護士のレベルは上がり、経済的にも強くなりました。必要ならば日本人を雇うこともできる。「さすがに大国だなあ」というのが偽らざる感想です。
中国事業拡大を目指し帰国。その目は今、アジア全域から世界へ

2000年、曾我はアンダーソン・毛利法律事務所を辞して独立するとともに、帰国する道を選ぶ。蓄積したノウハウを生かして中国ビジネスを拡大するうえで、従来のポジションの限界を感じたからだ。同年、中国業務開拓の草分け的存在である糸賀了弁護士などと新たな事務所を組織、真の意味での経営者となった。
ゼロからスタートして、ようやくベースを築いた北京を去るのは、正直一大決心でした。ただ、現地にいて受任できるのは、相対的にみると小さな案件に留まります。中国への投資や撤退、現地での経営に関連する各種法律問題、契約書の作成、通商など、帰国後も中核業務の中身は基本的に変わりませんでしたが、やはり日本企業相手に大きな仕事をしようと思ったら、東京なのです。そのことを、日本に戻って実感できました。ただ、中国をめぐる環境は、その後大きな変化を遂げました。世界の工場から一大消費地へ。日本企業も製造拠点の立地を東南アジアにもシフトするという状況が出現しました。弁護士業務という切り口でみても、さっきも言ったように中国の弁護士のレベルが向上した結果、以前と同じことをやっていて仕事が増やせる状況ではなくなったのです。
今の事務所は、私を含むパートナー6名をはじめとする弁護士11名、会計士1名、加えて中国、ベトナム、インドなど外国弁護士6名の陣容です。中国がメインであることに変わりはないのですが、そのウエートは売上ベースで5割くらい。残りは東南アジアを中心とした世界に広がっています。
自分の中で多角化の嚆矢になったのが香港上場の仕事。11年、日本企業の香港上場を請け負ったのがきっかけです。中国の一部とはいえ、香港市場の仕事はまったく別のアプローチが必要でした。その後も日本企業や日本ビジネスを行うアジア企業の香港上場案件での日本法顧問をお任せいただいています。現在の事務所を立ち上げてからは、「会社の国際法務を丸ごとみてほしい」という依頼を受けることも多くなりましたね。いきおい地域も業務もバラエティに富んでいくわけです。
「今後もアジアを中心に新たな方向を模索していく必要がある」と語る曾我だが、同時に「それは私ではなく、若い人たちの仕事だ」と言い切る。言葉の裏にあるのは、「自分は“弁護士道”を貫く」という確固たる信念だった。
現事務所として独立する前、瓜生健太郎弁護士と共同経営をしていました。彼は弁護士という枠にとらわれず、会計なども含めた総合的な専門家コンサルティングビジネスを構築する、というタイプ。対照的に私は、アンダーソンで叩き込まれた三つ子の魂百までというか、とにかくLawyeringに徹していないと気が済まないタイプ。お客さまが「曾我に」と来たのなら、別の人に任せきることがなかなか難しい。瓜生さんと共同経営したことにより、自分のそのような習性を多少なりとも調整することができたという点で有益でした。でも、逆に彼我の比較においてやはり変わり切れない面があることを認識し、“自分は自分”的に達観できたという意味でも非常によかったと思っています。そんな自分流の私は、自分を信頼して依頼してくれるお客さまから頂戴する目の前の仕事をこなしていく。“次の市場”的なことは次の世代に考えてほしい。いいアイデアだったら全力で応援するよ、というスタンスを基本にしています。
振り返ってつくづく思うのですが、今現在の自分は、決して予測の上にこうなったわけではないのですね。米国留学を志した時、中国に渡るなんて、露ほども思わなかった。私に限らず自分の将来を見通すことは難しいと思うのです。プラスαのつもりで1年程度滞在して戻ってこようと思っていた北京に6年間居たのは、単にその時点でそこにニーズがあったからです。
同志として長年一緒に仕事をしている弁護士も、また私の下で仕事をして巣立っていった弁護士も、その人ごとに眼前にあるニーズ、それは多種多様なのですが、とにかく、そのニーズを掴んで努力した人は相応に成功しています。だからこそ若い人たちに考えてほしいのは、何かを狙うことも大切ですが、それ以上に目の前のニーズを敏感に察知して“食らいつく”姿勢を大事にしてほしいということです。とりわけビジネスロイヤーにとっては、それが仕事に向かう基本姿勢だと私は感じています。
あとは人との出会いを大切に。通商を業務に取り入れるきっかけになった孟さんとのつき合いは、今でも続いています。どんな偶然が新天地に導いてくれるかわからない。そんな発想、大事にしてほしいですね。
※本文中敬称略









