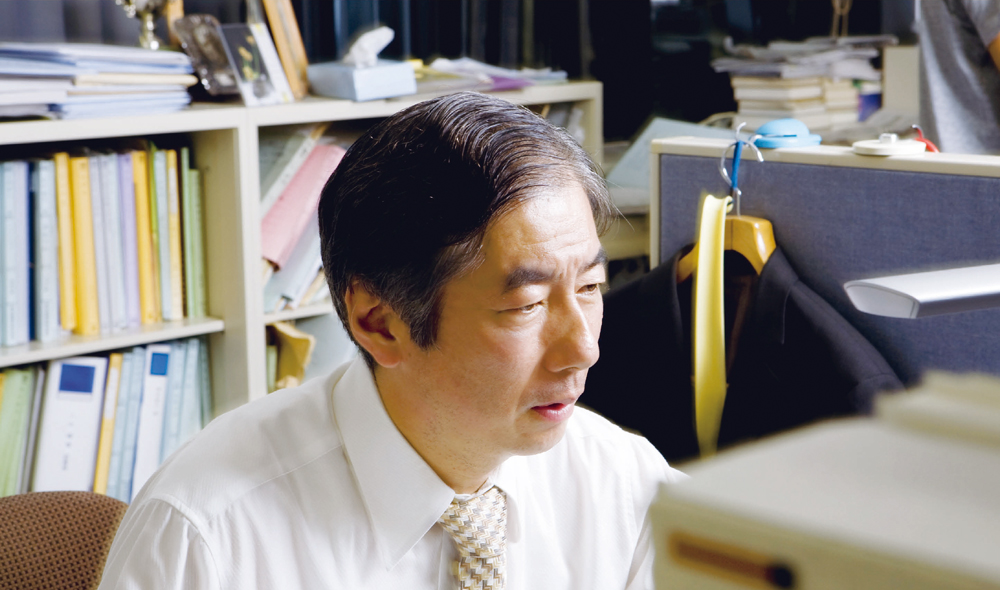1952年、東京生まれ。平凡なサラリーマン家庭で育った安原氏の周囲に法曹関係者はいなかった。実は東京大学法学部に入学するまで、「司法試験」の存在すら知らなかったというから驚きである。当時の安原青年を夢中にさせていたもの。それはスポーツだった。
「高校時代は陸上競技、大学に入ってからは、アメリカンフットボールに明け暮れましてね。それこそ大学1年のときは、24時間アメリカンフットボールのことばかり考えているスポーツ馬鹿でした(笑)」
だが、それから間もなくして、練習中に手首を骨折。これが安原氏の運命を変えることになる。
「練習に出られず、フラフラしている僕を見た友人に誘われましてね。裁判の支援活動でした。生活保護の不正受給を疑われている被告の無罪を一緒に勝ち取ろうと」
大学や高校が学生紛争で荒れていた時代である。自らその運動に身を投じることはなかったが、権力や権威の存在は意識していた。
「その頃から、社会的に弱い立場の人を助けてあげたいとか、権力から守ってあげたいという思いがあったのでしょう。それで、このときに知り合った1年先輩に言われたんです。『お前、司法試験でも受けてみたらどうだ』と。それで、弁護士に関心を持つようになったんです」
司法試験は在学中に一発で合格。弁護士としてのスタートの場には、東京の下町・蒲田にある東京南部法律事務所を選んだ。
「環境の整った都心の事務所じゃなくて、少しくらい不便なところで、自ら苦労を買って出てこそエリートだ、選ばれた者の役目だと思っていましたからね。それこそ、エリート意識プンプンでした(笑)」
入所から約10年間は、労働事件を中心に数多く取り扱った。事務所の近くに羽田空港があったこともあり、当初は航空関係企業の解雇事件などの処理に追われた。
「ほかにも、ありとあらゆる事件に携わり、ひたすら仕事をこなす日々。おかげで、案件処理の能力はずいぶんと磨けたんじゃないかな」
弁護士の力には2つある、と安原氏は言う。事件を処理する能力と、事件を引っ張ってくる能力。20代は、後者の力は小さく、前者が圧倒的に強い。30代に入ると、事件を引っ張ってくる能力が高くなっていくが、処理能力が衰えていく。さらに40代に入ると、今度は引っ張ってきた案件を自分で処理しきれなくなる。
「そこで、仲間の力やネットワークを活用して、うまいこと仕事をこなしていくようになるわけです。ただ、自分が50代になったときのことまでは、考えていませんでした(笑)」
実際、自分が培ったノウハウを次代に継承していかねば、と気付いたのは、50代に入ってからだという。そこにたどり着くまで、ずいぶん長い時間を要したものだと思われるかもしれないが、彼の活動を振り返ってみれば、もっともなことだ。東京HIV訴訟が始まったとき、安原氏は35歳になっていた。以来、難度の高い訴訟や救済活動に次々と関わり、怒濤の日々を過ごすことになるからである。