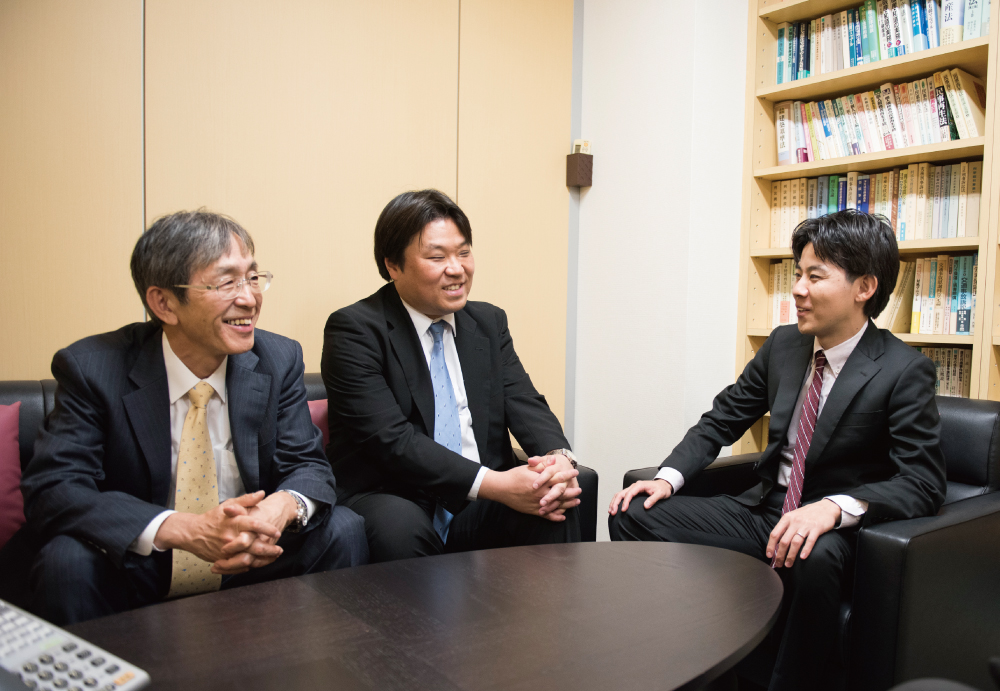前列左より、齋藤祐一弁護士(32期)、奈良道博弁護士(26期)、井上裕明弁護士(48期)、2列目左より、三浦繁樹弁護士(51期)、岩田拓朗弁護士(44期)、奈良ルネ弁護士(27期)、北村聡子弁護士(51期)、3列目左より、佐藤祐子弁護士(55期)、菊地康太弁護士(60期)、野﨑修弁護士(43期)、佐々木茂弁護士(59期)、鈴木克哉弁護士(新63期)、4列目左より、飯島智之弁護士(新63期)、長谷川和哉弁護士(新64期)、市野澤剛士弁護士(67期・公認会計士)、他に弁護士は4名
前列左より、齋藤祐一弁護士(32期)、奈良道博弁護士(26期)、井上裕明弁護士(48期)、2列目左より、三浦繁樹弁護士(51期)、岩田拓朗弁護士(44期)、奈良ルネ弁護士(27期)、北村聡子弁護士(51期)、3列目左より、佐藤祐子弁護士(55期)、菊地康太弁護士(60期)、野﨑修弁護士(43期)、佐々木茂弁護士(59期)、鈴木克哉弁護士(新63期)、4列目左より、飯島智之弁護士(新63期)、長谷川和哉弁護士(新64期)、市野澤剛士弁護士(67期・公認会計士)、他に弁護士は4名
STYLE OF WORK 事務所探訪
#87