〝人権の縮図〟で培われていった弱者に味方する精神
「川人さんのおかげで、娘の尊厳を守ることができましたし、私が今生きていられるんだと――」。2015年暮れ、電通の新入社員だった高橋まつりさんが、1カ月100時間を超える残業を課せられた末に自殺した事件は、社会に大きな衝撃を与え、「働き方改革」推進のきっかけともなった。まつりさんの死の労災申請につき、遺族代理人となり、労災認定を勝ち取ったのが、川人博だ。冒頭の言葉は、川人を取材したNHK『プロフェッショナル仕事の流儀』で、まつりさんの母親・幸美さんが語った感謝の一言である。
1988年、「過労死110番」の運動にかかわった頃、それは「自己責任」とされ、遺族が救済されることはなかった。企業責任を認めさせるところまで世の中を動かすうえで、「過労死問題の第一人者」が果たした役割は、計り知れない。「根底にあるのは、人間の命と健康にかかわる仕事がしたいということ」。その意志は、いかにしてかたちづくられていったのだろう。
大阪の泉佐野市の出身です。1949年生まれというのは、団塊世代の“末っ子”でね。2つ3つ年上の子たちも含めて、とにかく大勢で夏は近くの海で泳いだり、かけっこしたり、缶蹴りしたり。終戦直後の田舎は、どこもそんな感じだったんじゃないでしょうか。
父親は開業医でした。もともと旧満州にいて、そこで医師免許を取ったのだけど、肺炎を患って真珠湾攻撃の直前くらいに日本に戻ったんですよ。今から考えると、運がよかった。
まだ国民皆保険になる前だったけど、地域には貧しい人もたくさんいて。父親はそんな人たちも「お金はいいから」と診察していました。夜中にドンドン玄関をたたく人はいるし、電話はかかってくるし。とにかく大変な仕事なのだな、と子供心に思っていましたね。ただ、医者の家に生まれた以上、自分もその道に進むのだろう、と漠然と考えていたんですよ。
ところが、小学3年か4年だったか、色覚検査で赤緑色弱と診断された。今でも、「博は医者にはなれへんかも」という母親の言葉が耳に残っています。

とにかく頭数の多い同世代の中、小学校の高学年ぐらいになると徐々にリーダーシップを発揮するようになっていた川人少年は、中学校の最終学年で生徒会長を務めた。ただし、そこには“荒れた”という言葉では表現しつくせない現実があった。
当時、高校に進学するのは2人に1人くらい。貧しい家庭では、早く卒業して稼がねば、という時代だったんですね。3年生になると、A~Dクラスが進学組、E~Hは就職組と分けられて。就職組の人間は、当然勉強へのモチベーションが下がるし、なにより面白くないわけです。そうすると、今みたいに引き籠ったりするのではなく、進学クラスに出かけていっては、授業の妨害を繰り返す。
教師が注意すれば、かまわず殴りかかる。教師はそれに応戦する。体罰も暴力も、ごく普通の環境でした。加えて、私の住んでいた地域には、同和問題や在日朝鮮人の人権問題が存在しました。また、これとは別な問題ですが、近くに暴力団事務所もありました。
要するに、差別、偏見、暴力、貧困といったものが、教育現場に剥き出しになっていた。よく言うのですが、〝人権の縮図〟みたいな学校だったんですよ。そうしたものは、時代や社会の矛盾の反映にほかなりません。そこにいた思春期の我々も、教員たちも、あるいは“非行”グループも彼らなりに、“時代と格闘”していたというのが、正確な言い方になると思います。
私には、今も引きずる思い出があるんですよ。卒業式の日、その中学だけでなく市内随一の“番長”と目される男が講堂で悪さをしているのを見つけて、注意したんですね。すると、「ちょっと来い」と腕を掴まれて、近くにある池まで連れていかれた。池の浅瀬に立たされて決闘寸前、というところで「やめろ!」と間に入ってくれたのが、S君という同級生でした。
すると番長は、「なにを!」とS君に標的を変えて、二人の喧嘩が始まってしまった。ある意味、自分が蒔いた種なのだし、今度は私が止めに入る番です。ところが、なぜかそのまま立ち竦んでしまった……。
結局、騒ぎを聞きつけた先生たちが二人を引き離してその場は収まりました。でも、どうしてあの時、制止できなかったのか? 人生には、想定外の困難や苦境にぶち当たることもあります。そうした時に、自分はどう振る舞うべきなのだろうという自問自答が、その痛い思い出とともに、今も頭の中で続いています。
そんな“事件”も含めて、あの環境が私にいろんなことを考えさせてくれたのは確かです。「これまで生きてきた中で、今に一番影響を与えているのはいつか?」と問われたら、迷わず「中学校の3年間」と答えるでしょうね。
経済学に目覚め東大へ。公害裁判に感化され弁護士を目指す
壮絶といっても過言ではない中学時代から一転、進学した府立三国丘高校には、学びの環境が整っていた。一方、入学して始めた柔道では、半年で昇段試験に合格し、黒帯に。やがて主将を務めるほど打ち込んだ。多くの恩師と出会い、友人たちと語らう中で、徐々に社会に対する関心を高めていったのも、この時期だった。
私が高校時代を過ごした60年代後半というのは、ベトナム戦争の影響もあって、日本社会にもどことなく反体制的な雰囲気が漂っていたんですね。高校の先生の影響もあって、私も2年生ぐらいから、社会的な問題を強く意識するようになりました。
特に興味を持ったのは、当時は社会科学として比較的メジャーだった、歴史学や経済学だったんですよ。「歴史とは、現在と過去の間の尽きることなき対話」という一文で有名なE・H・カーの『歴史とは何か』の読書会をやったりしたことを覚えています。
お話ししたような事情で医者の道をあきらめていたから、将来何になろうか、真剣に考えるべき時でもありました。そこで選んだのは、経済学だったんですよ。当時は、マルクス経済学とケインズ経済学という大きな2つの流れがあったわけですが、いずれにしても社会全体を考えて、どのような政策を立案する必要があるのか、という社会変革の立場に立った学問であることに魅力を感じていたのです。
受験に関していえば、私にはアドバンテージがありました。2つ上の兄が医者を目指して東大に進学していたのですが、同じ部屋で勉強していたから、ずっとそのやり方を見ていたのです。だから、「このくらいやればいいんだな」というのが、なんとなくわかる。現役合格できたのは、兄のおかげです。
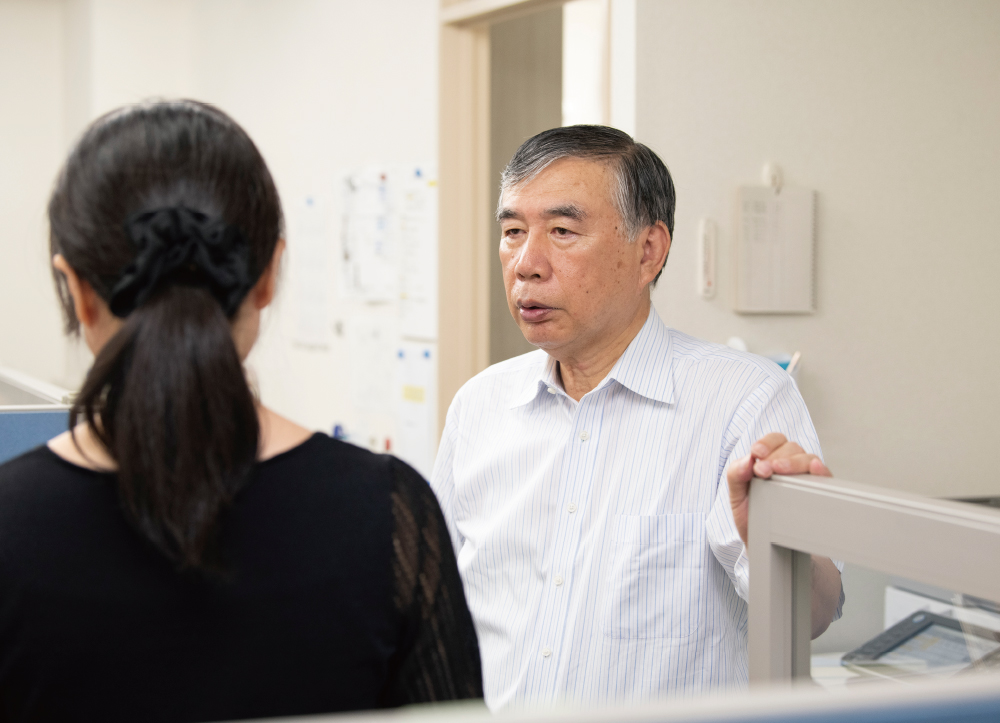
こうして68年、川人は晴れて東大文科二類に合格するのだが、待ち受けていたのは、折しもピークを迎えた「東大闘争」だった。入学後、2カ月と経たずストライキに突入した大学は、「勉強ではなく、ほとんど集会かデモをする場所」と化していた。
勉強したい人間は家でやっていたのですが、私はキャンパスにいた(笑)。大学改革、まだ返還前だった沖縄問題、安保、ベトナム反戦と、闘争課題には事欠かない時代です。結局、2年で出るはずの教養学部に4年いました。
そんな状況だから、まともに経済の勉強を始めたのは、経済学部に進級してからです。それでも、卒業が近くなるまで、大学院に進むつもりでいたんですよ。ところが、そこから司法試験の受験に方針転換するのです。大学闘争の後遺症もあって、大学院の教育体系が乱れていたというのもあったのだけど、それよりも大きかったのは、友人たちの多くが弁護士を目指していたことでした。
教養学部では、法学部と経済学部に進む人間が、同じクラスになります。だから“友人たち”というのは法学部生なのですが、彼らが「川人は弁護士のほうが向いている」「院なんかやめて、俺たちと勉強しよう」と言うわけです。
彼らの誘いに応じたのには、自分なりの理由もありました。ちょうど大学に入る前後に四大公害(新潟水俣病、四日市喘息、イタイイタイ病、熊本水俣病)訴訟が始まりました。そこで大活躍したのが弁護士だったのです。
弁護士といえば、せいぜい「罪のない被告人のために奔走する」というイメージ。それが、「命と健康を守るために、住民と共に戦う」「全力で企業の不正を暴く」存在として、大きくクローズアップされました。そんな公害裁判に感化されて弁護士を目指した学生が、当時どれほど多かったことか。法学部の授業など1時間も出たことがないのに司法試験にチャレンジしようという人間は、そうはいなかったかもしれませんが(笑)。
今のような予備校もない時代、同じ出身大学の合格者の指導を受けるというのが、受験勉強のやり方でした。実質1年半くらいの勉強で合格できたのは、やはりそんな仲間や先輩たちのおかげというしかありません。
21世紀まで続くとは思わず着手した過労死問題

弁護士は“他律的”な存在。私はたまたま「過労死の時代」に生き、その要請に応えた
78年、司法修習を終えた川人は、文京総合法律事務所に所属し、弁護士としての一歩を踏み出す。そこでは、刑事事件のほか、交通事故、労働事件、サラ金被害、知的所有権をめぐる争いなど、「最初の10年は、本当にいろんなことをやった」という。
当時は「急性死」といっていたんだけれど、激務を重ねていた人が、突然くも膜下出血で倒れたというような過労死案件も、すでにありました。そうかと思うと、億単位の不動産取引の立ち合いをやったりね。受け渡しが終わって、「日当は3つで」と言うので3万円の領収書を切ろうとしたら、100万円の束が3つだった(笑)。
とにかく、駆け出しの頃からいろんなものを“見た”わけで、それがみんな糧になったのは間違いありません。若い人に言うのだけれど、条件が合うのなら、多様な事件をやったほうがいい。最初から「自分はこれが専門だ」というスタンスでいくと、どうしても視野が狭くなってしまうと思うのです。
ちなみに、私は今でも「過労死事件は9、残りの1は別の分野でいこう」と心がけています。ものの見方、考え方が偏らないようにするには、それが大事だという実感があるからなんですよ。例えば同じような相続や離婚の紛争でも、実際に取り組んでみると中身はそれぞれ違う。時代の変化に気づいたりすることもあるのです。そういう経験は、過労死の案件を扱う時にも、大いに役立つわけです。
その過労死の事件に取り組むようになったのは、88年に、「過労死110番」の活動に参加したのがきっかけだ。問題の深刻さは認識していたものの、「文字どおり、電話が鳴りやまない」状況は想像を超えるものだった。しかし、受話器から聞こえる悲痛な訴えとは裏腹に、行政の壁は厚く、労災認定が認められるのは極めて稀という現実に直面する。
夫や子供を失った遺族が実情を訴える場はできたけれど、救済はされない。これはきつかった。そこで私は、労災認定に頼るだけでなく、直接企業を相手に裁判を起こすべきだと考え、実行に移したのです。
89年、富士銀行(現みずほ銀行)の20代前半の女性行員が、持病の喘息を悪化させて亡くなりました。「働き過ぎが原因だ」と銀行に損害賠償を求めたのが、過労死裁判の第1号です。この裁判では、勝利的和解を勝ち取ることができました。
画期的だったのは、93年から始まった電通過労死事件訴訟です。私はこの訴訟を最高裁の段階から担当しました。月に140時間を超えるような残業を強いられた男性社員が、うつ病になって自殺したのですが、2000年に、初めて過労死の企業責任を認める最高裁判決が出ました。
日本の人権裁判史上、十指に数えられると評されるような最高裁判決を経て、行政も変わりました。厚生労働省が、相次いで過重労働に関する通達を出し、過労死の労災認定基準も新たに策定されたのです。裁判というものが、社会に対していかに大きなインパクトを与えるものなのか、私自身あらためて勉強になった。それらを含めて、今までに遺族代理人になり担当した過労死事件は、500件を超えます。
ある著名な弁護士さんに、「川人さんたちの活動は極めて先進的で、弁護士の役割をまた一段広げた」と言われたことがあるんですよ。でも、それはちょっと違う。88年に「過労死110番」の取り組みを始めた頃、そこに集った全国で20人ほどの誰もが、21世紀になっても同じようなことをやっているとは、考えていなかったでしょう。そもそも先見性も何も、目の前の相談に対処するので精一杯だった。
考えてみれば、弁護士の仕事ってそういうものでしょう。依頼者がいなければ成り立たないのだから、ある意味“他律的”なのです。私の場合は、「貧しい人のために」「人の命と健康を守るために」というものが根底にあったわけですが、それがたまたま過労死という現象と出合い、弁護士としてそこに全身全霊を注ぎ込むことになりました。作家のように、自分で筋書きを書いたわけではないのです。当時は、バブル経済の絶頂でもありました。「稼げ、稼げ」という異常な環境が長続きするはずはない。いつかは落ち着く、という気持ちもどこかにあったのは事実です。ところが、バブルは崩壊したのだけれど、過重労働はなくならない。逆にメンタルなストレスが増大して、自殺が非常に増えてきたわけです。
過労死の企業責任が認められ、以前に比べれば制度も整備され、14年には過労死防止法という法律までできた。でも、実際には、「第2の電通事件」が起きてしまったように、30年前となんら変わらぬ現実があります。「10年経ったら、過労死は消えてなくなっているか?」。その問いにはっきりとイエスと答えられない現状は、やはりなんとかしなければなりません。
リタイアの発想は封印。実践とともに蓄積の整理に注力する
折しも「働き方改革関連法案」が成立したものの、そこには「かえって過重労働を増やす危険性がある」という指摘もある。川人が述べるように、過労死問題の行く末は、不透明だ。ところで、そんな川人に「若き弁護士に対するメッセージを」と水を向けると、少し考えた後、口をついたのは、「私は時代的に恵まれていたかもしれません」という言葉だった。
さっき、「駆け出しの10年間でいろんな事件を担当したことが財産になった」と言いました。そんな話をすると、若い人たちは「それは、先生の時代だからできたこと」と思うかもしれませんね。確かに、今は弁護士人口の問題もあって、一人がたくさんの案件を経験すること自体、難しくなっている。
ただ、一つの事件に取り組む場合にも、多様な視点から考え、いろんな実践をしてみることが大事だ、と私は思っているんですよ。その点で、少々もどかしさを覚えるところもあるのです。
例えば労災事件で、夫を亡くした奥さん、子供を失った親御さんに会って話を聞きますよね。今は仕事量と体力の関係でなかなかできないのですが、私が若い頃は、可能な限りご自宅に行って話を聞くようにしました。そうすると、亡くなった人間がどんな環境で育ったのかだとか、事務所のデスクで相対するのでは得られないものを体感できるわけです。
あるいは、過労死の現場が自動車工場ならば、自動車産業が今どんな状況にあって、この工場がどういうポジションに置かれているのかを調べてみる。そうやってバックグラウンドを知るだけで、訴状の“厚み”が違ってくるはずなのです。
あえていえば、今は当該事件の労働環境がどうだったとか、残業時間がこれだけあったという事実さえ押さえたら、裁判に勝てるかもしれません。しかし、それだけで遺族の無念の思い、「過労死の根絶を」という社会の要請に十分応えたことになるのか? なにより、本人が弁護士として成長していくために、それでは足りないのじゃないか、と私は感じるのです。
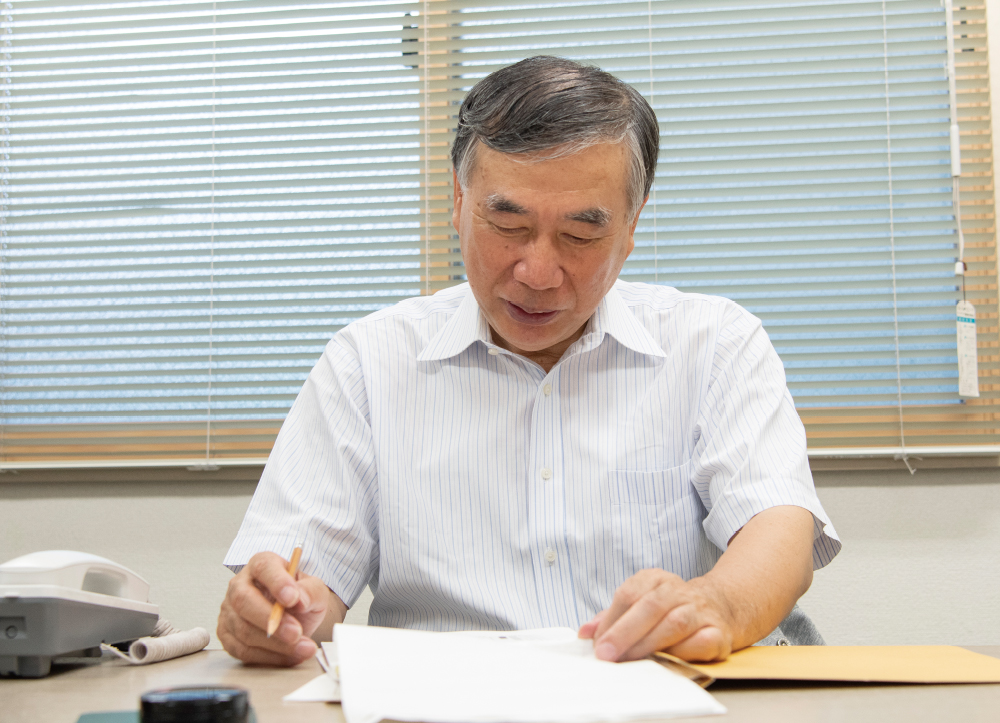
今年10月で69歳になる。実は還暦を迎えた際には、「65歳でリタイアしよう」と心に決めていたのだが、現実がそれを許してはくれなかった。次に定めた“定年”は70歳。しかし、そこまで1年あまりとなった今、自らに年齢制限を課すのはやめたそうだ。
幸か不幸か、医者や弁護士は、自分にやる気さえあれば、何歳でも続けられる。「ほかの職業ではできないことなんだ」と割り切って、「何歳まで」という考え自体を撤廃することにしました。
ただ、仕事の中身は若干変えていくつもりです。実践にプラスして、40年間積み上げてきた蓄積を、単なる事件記録としてではなく、後世の人たちが役立てられるようなかたちに整理したい。整理には、法律的にだけでなく、経済学的、社会学的……いろんな分野、切り口があります。整理したうえで、理論化する作業も必要になるでしょう。
過労死に関しては、これまで、遺族の思いを行政や企業にぶつけて、その姿勢を変えさせていくという活動がメインでした。それはこれからもそうなのだけど、一歩進んで、企業の内部に「長時間労働はいけない」と真剣に考える人を増やしていくことが、大きなポイントになるというのが、私の考えです。過労死防止法ができて以降、企業から講演を頼まれる機会が増え、今年は四半世紀ぶりぐらいに経団連からも声がかかりました。そうした場も通じ、本当の意味で企業を変える努力を重ねていきたいんですよ。
加えて私に課せられた重要な任務は、後継者の育成です。過労死問題に関する社会活動を継続するためには、それを担う人を育てなければいけない。
育てるという意味では、講師をしている東大教養学部の「法と社会と人権」ゼミからは、いろんな分野で活躍する卒業生が巣立っているんですよ。フィールドワークを中心に据えた活動は、27年になりますけど、これにも“定年”を設けるつもりはありません。
よく、「生まれ変わったら、また弁護士をやりたいですか?」という質問を受けることがあります。私の答えは「いいえ」。弁護士が嫌いというわけではないのです。もう1回人生をやれるなら、医者なり経済学者なり、別のことをやってみたい。
ともあれ、この世で私は、たまたま弁護士になり、たまたま過労死問題と向き合うことになりました。それが使命だと思うから、力の続く限り頑張りたい。あらためて、それが70歳を前にした今現在の決意表明です。
※本文中敬称略
※本取材および撮影は、東京都・文京区の川人法律事務所で行われた。現在、同事務所の弁護士は川人氏1人。2人の秘書が、多忙な川人氏の業務をアシストしている









